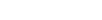エモーショナルインテリジェンス(EI)とは、自己の感情を理解・調整し、他者と円滑に関係を築く能力です。職場では、チームワークやコミュニケーションの向上、ストレス耐性の強化に寄与し、組織全体の生産性を高めます。育成には、自己の感情を言語化する習慣や傾聴、自己反省の実践が効果的です。リーダーや管理職はEIを高めることで、職場の雰囲気や従業員のモチベーション向上に貢献できます。今回は、エモーショナルインテリジェンスの重要性や高め方などについて解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>エモーショナルインテリジェンスとは?
自己の感情を理解・調整し他者と円滑に関係を築く能力
エモーショナルインテリジェンス(EI)は「心の知能指数(EQ)」とも呼ばれ、端的に言えば「自己の感情を理解し、意識的に調整し、他者との関係の円滑化に活用する」能力であるといえます。
現在普及しているEIの概念は、1990年代に心理学者のDaniel Goleman氏によって提唱されたものです。氏はこの能力を「自己認識力」「自己抑制力」「モチベーション」「エンパシー(共感力)」「社交スキル」という、5つの構成要素で成り立つものと定義しています。
IQとの違いやエモーショナルインテリジェンスの重要性
「IQ(知能指数)」は、言語理解や計算など「明確な答えの存在する」問いに対して、素早く正確に回答を導き出す能力です。対してEI・EQは、感情の動きという「明確な答えがない」問いに対し、論理的思考と感情の両面から考察し、適切と思われる回答を導く「知性」といえます。
「知能」と「知性」は、似ているようで異なる概念です。例えば数学的分野で高いIQを発揮し、コストの概算などを素早く提示できる有能な人材が、いざ営業職として現場に立つと、目の前の顧客の感情・ニーズを読み取れず成績が奮わない、というケースがあります。こういったケースでは、IQの高低とは直接関係のない、営業職としての成功に必要なEIの欠如が表面化しているといえるでしょう。
エモーショナルインテリジェンスが求められる理由
エモーショナルインテリジェンスは、上述のような個人の成果のみに留まらず、集団としてのチームワークや、それをまとめあげるリーダーシップの発揮にも貢献します。そのため組織においては、管理職のみならず全ての人材について、EIへの理解と向上の取り組みが重要といえます。
中でも特に重要性が高いといえるのが、職場の「心理的安全性」に寄与し、チーム全体のパフォーマンスを高める効果です。リーダーの持つEIの能力は、メンバーにとって発言しやすく、同調圧力やストレスの少ない職場環境づくりに直結します。また各々の持つEIによって、個人が自発的に考え、対等の立場で議論を行える雰囲気が醸成されれば、従業員エンゲージメントの高まりによってチームワークが促進され、ひいてはRoIの向上も期待できるでしょう。
エモーショナルインテリジェンスを構成する4つの能力
感情の識別
感情の識別とは、怒り・悲しみといった感情の種類を推察し、感情を俯瞰的に捉えることを指します。自身の感情を一歩引いて論理的に捉えることで、他者の感情についても同様に識別することが可能となります。
感情の利用
感情の自己認識ができるようになれば、その感情に振り回されるのではなく、自己の精神統一や、チームの統率のために自覚的に利用することもできるでしょう。例えば白熱する議論の場など、論理的思考力が必要な場面で冷静さを取り戻したり、反対にチームが消沈しているような状況で、前向きな対応を打ち出して再起を促したり、といった例が考えられます。
感情の理解
「感情の識別」と似通った概念ですが、感情の原因を理解することもエモーショナルインテリジェンスの一環です。原因が特定できれば、その変化を予測して対応するだけでなく、原因そのものに対処することが容易となるでしょう。
例えば理由もなくイライラしているように感じる時、対症療法的にただ発散に向けて動くのではなく、「身体の疲労」「目標の未達」「人間関係のトラブル」といった原因の構成要素を切り分けて考えるのが、この一例です。
感情の整理
上記3つの能力を適切に活用する能力が「感情の整理」です。直前の例で言えば、3つのイライラの原因どれに重点を置いて解決を図るべきかを判断し、優先度に応じた解決策を実行に移すことが、この能力に該当します。
やや抽象的な表現になりますが、総括すると「感情の仕組みを理解した上で、場面ごとに有効な感情を喚起し、具体的かつ適切な行動へつなげる能力」といえそうです。
エモーショナルインテリジェンスの高め方
自己の感情を認識する能力を鍛える
自己の感情を一歩引いた視点から、俯瞰的に認識する力は「メタ認知」とも呼ばれます。エモーショナルインテリジェンスの向上には、このメタ認知の習得が必須といってよいでしょう。
メタ認知習得の第一歩としては「メタ認知的セルフチェックリスト」の作成が有効とされています。このチェックリストは「起きたこと」「その時の感情」「身体反応」「取った行動」「結果」を書き記すもので、1日の終わりに振り返りとして実施するのが効果的です。
これにより、感情の発生原因から結果までを細分化して客観視でき、比較的短期間でのメタ認知力向上に役立つ可能性があるでしょう。
エモーショナルインテリジェンス育む組織文化をつくる
組織としてエモーショナルインテリジェンスの向上を推進したい場合には、人事評価制度や教育・研修制度にEIの考え方を組み込むことも有効です。
例えば従業員へは同僚や取引先との関わりにおけるEIを、管理職にはチームワークにおけるEIを、それぞれ教育する機会を設けるとともに、評価項目にも「傾聴の態度」など、それらを点数化する視点を取り入れます。また、さらに高度なフィードバック体制を整えたい場合は、感情分析に特化したチャットボットや、匿名フィードバックプラットフォームなどのITインフラを導入するのもひとつの手かもしれません。
ただし、組織の構造や成熟度、企業風土等によっては、EIの組織的な推進により金銭的・時間的なコストが重荷となり、評価制度が複雑化する可能性も考えられます。費用対効果の検討は、長期的な視点で二重三重に行う必要があるでしょう。
まとめ
メタ認知により感情を客観的に分析し、行動に活かす「エモーショナルインテリジェンス」は、自身のみならず周囲の人間や、職場環境にも好ましい影響を及ぼす能力です。組織においてはプレーヤー・マネージャーの別を問わず、EIを習得ならびに向上することが、パフォーマンスの安定的な発揮に重要な役割を果たします。個人による自発的なEIの向上にはメタ認知セルフチェックリストの作成が有効であるほか、組織的に教育・人事評価制度に組み込むことによって、より総体的な底上げを図ることもできるでしょう。