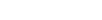中心化傾向とは、評価者が極端な高低を避け、真ん中に近い評価をつける傾向を指します。リスクとして、優秀な人材や課題を抱える人材を正しく見極められず、人事評価や人材活用の精度が下がる点が挙げられます。改善方法には、評価者研修の実施や多面評価(360度評価)の導入、評価基準の明確化などが効果的です。人材の適正評価を実現するために、組織として継続的な取り組みが求められます。今回は、中心化傾向のリスクや改善方法などについて解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>中心化傾向とは
人事評価エラーの一つ
人事評価の基準やプロセスは、企業によって定められた内容に沿って実施されるのが一般的です。しかし、その評価基準やプロセスが何らかの理由で曖昧になっている場合、評価者の主観のもと対象者を評価せざるを得なくなってしまいます。主観による評価が進めば進むほど、その評価基準は偏った内容となってしまい、これが人事評価エラーにつながる要因の一つと言えるでしょう。このうち「中心化傾向」は、「とても良い」「とても悪い」などの極端な評価を避け、「標準的」「平均」など高くも低くもない中央値に評価内容が集中してしまう現象のことを指します。
中心化傾向が発生する要因
評価基準そのものに問題があるケースのほかにも、中心化傾向が発生する要因はいくつか考えられます。例えば、評価者が対象者の業務内容や実績を明確に理解しておらず、判断材料が足りない状態で評価を実施しているケースです。評価対象者との接点が少なかったり、コミュニケーションが少なかったりする現場、もしくは一人の評価者が多くの従業員を対応しなければならない場合などがこれに当てはまります。次に、評価対象者の気持ちを必要以上に気にしてしまい、本来の評価基準とは異なることを理解しているものの、無難な内容にまとめるために評価を中心化させてしまうというケースも考えられます。
中心化傾向以外の人事評価エラーの種類
人事評価エラーには、中心化傾向のほかにもいくつか傾向があることが知られています。代表的なものとしては、「ハロー効果」「寛大化傾向」「厳格化傾向」などが挙げられます。まずハロー効果は、一つの突出した良い評価、もしくは悪い評価が発生すると、本来は関連性がないはずなのに他の評価内容もそれにつられてしまう現象のことを言います。寛大化傾向や厳格化傾向は、名称の通り実際の評価基準にかかわらず全体的に甘い評価にしてしまうこと、もしくは厳しすぎる評価をしてしまうことを指します。
中心化傾向が発生した際のリスク
従業員を正当に評価できない
人事評価による内容を、昇進や人材配置を実施する基準の一つとしているケースも少なくありません。その評価が適切に行われていない場合、チームや組織全体の生産性や効率が低下してしまう可能性があります。過大評価によって本来の能力や適性にそぐわない、本来の力量を超えたポジションや業務を任されてしまうと、ヒューマンエラーの増加や精神的ストレスを抱えるリスクが高まるでしょう。
従業員のエンゲージメント低下
反対に、本来よりも過小評価されたケースも非常に深刻です。中心化傾向になってしまった評価を見た評価対象者が、自分自身を正当に評価されてもらえないと感じた場合、評価者や企業への信頼感を失いかねません。評価者となる上司や上層部への信頼感が悪化し、両者の関係性が悪化することが危惧されるでしょう。また、業務へのモチベーションが下がることで本来のパフォーマンスを維持できなくなり、さらに評価が下落するという悪循環に陥るケースも考えられます。
人材流出への懸念
エンゲージメントやモチベーションが低下してしまった従業員は、最悪の場合離職や転職を考えるケースも十分に考えられます。人材不足が課題となっている現代社会では、人材流出は企業にとって大きな痛手となることは間違いありません。「正当に評価してもらえないなら辞めるしかない」と従業員から思われているということは、正当な評価を維持できていないということの表れであり、早急な評価エラーの改善が求められるでしょう。
中心化傾向の改善方法
評価基準の明確化
まず、評価基準が曖昧という問題がある場合は、評価者の主観によってバイアスがかかりやすい・かかりにくいという問題が発生する可能性があります。そのため、評価者が誰であっても客観的に対象者を評価できるような基準を構築することが重要です。特に、「積極性」や「コミュニケーション能力」など、一般的に数値で表しにくい項目に関しては、どのような基準をもって評価を行っているのか、また企業としてどのような能力や適性を求めているのかを事前に共有しておくのも良いでしょう。
多面評価の導入
評価基準を明確にしたとしても、主観やバイアスによる評価の揺らぎは、人が評価している以上どうしてもゼロにすることはできません。そこで、少しでも偏りを軽減するためには、複数人で評価を下す「多面評価」というプロセスを用いるのも効果的です。労力や時間はどうしても一般的な評価方法よりは増えてしまうものの、多角的な視点から評価を得られることから、評価対象者にとっても納得感の得られる客観的な評価が得られやすいというメリットがあります。
評価者に対する研修の実施
評価エラーが起こってしまう要因の一つとして、評価者が自身の評価内容に自信を持っていないという可能性も考えられます。公正かつ適正な内容で人事評価を行うためには、評価者研修を定期的に行い、評価基準や目的、注意点を共有し、評価者同士が一定の内容で評価を下せるようにすり合わせを行いましょう。また、中心化傾向をはじめ、人事評価エラーの代表的な事例をあらかじめ評価者同士で共有しておくのも、評価者同士の意識を高めるためにも有効な対策です。
まとめ
人事評価は、単に昇進や待遇改善を行う指標を示すだけではなく、人材育成の一環として行われる重要なプロセスです。中心化傾向をはじめ、あまりにも評価者の主観で結果が左右されてしまう人事評価は、企業へのエンゲージメントや働くモチベーションを低下させてしまうリスクも考えられるため、評価エラーを起こしにくい仕組みを構築することが重要です。