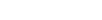さとり世代とは、1980年代後半〜1990年代後半に生まれ、安定志向・効率重視・無理をしない現実的な価値観を持つ世代を指します。ゆとり世代と比べ、内向的で「欲がない」「悟っている」といった姿勢が特徴とされます。仕事では無駄を嫌い、成果や合理性を重視する傾向があり、指導においては納得感を重視した丁寧な説明が効果的です。今回は、さとり世代の特徴と、ゆとり世代との違い、適切な関わり方などについて解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>さとり世代とは?
1980年代後半~2000年代前半に生まれ現実的な価値観を持つ世代
「さとり世代」とは、「悟っているような姿勢」「安定志向を好み欲がない」という点を特徴とする価値観を持つ、一定の年代生まれの世代を指す通称です。多くの場合、1980年代後半~2000年代前半に生まれた世代を大まかに指しますが、具体的に1987年以降生まれ、と定義されることもあります。
「さとり世代」という言葉が生まれた背景
さとり世代という言葉の初出は、インターネット上の匿名掲示板であるとされることが多いようです。それまでは限定的に使われる言葉であったものの、2013年の「新語・流行語大賞」にノミネートされたことをきっかけに、大衆に広く知られるようになったとも言われています。
さとり世代は、物心ついた頃(1993年ごろ)のバブル崩壊による不況に始まり、若年のうちに2009年のリーマンショックも目にしていることから、国内経済が明確に上向いた経験がなく、またこれから回復するという期待感が薄くなりがちです。また、1995年の阪神淡路大震災や、2011年の東日本大震災といった大災害にも直面した経験から、程度の差こそあれ、死生観に対しても他世代とは異なる考え方の傾向がみられるとされています。
さとり世代とゆとり世代の違い
「ゆとり世代」は、1987年から2004年に生まれ、2008年に改訂された学習指導要領に基づく、いわゆる「ゆとり教育」を受けてきた世代を指す言葉です。さとり世代とは出生期間が重複しており、混同される場合もありますが、ゆとり教育の功罪を明確にしたい文脈では区別するケースもあるようです。具体的には、この期間の前半に生まれた世代をゆとり世代、学習指導要領の見直しが検討されはじめた後半に生まれた世代をさとり世代、とするケースが散見されます。
ただし実際のところ、学校教育のカリキュラムが経済観・価値観の形成に深く関係するか、という点には疑問が残るため、両者は同じ世代の異なる側面を指しているだけ、という考え方もできるでしょう。
さとり世代の特徴
現実主義
さとり世代は一般に、実現性が低い希望を持つことに抵抗がある、という特徴があるとされています。「悟っている」ような印象を受ける一因であり、努力が可視化されやすい物事には力を入れて取り組む一方、挑戦をしたい、夢や大望を叶えたい、といった意識は薄いようです。これには、バブル期のきらびやかなブランド志向がその崩壊とともに一転し、社会全体が倹約志向に冷え込んでいく様を目の当たりにしてきた経験が関係していると考えられています。ビジネスシーンにおいては、企業の持つイシューやMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)等への共感が薄い可能性もあるでしょう。
非ブランド志向
日用品や衣服等についても、さとり世代はネームバリューよりも実用性やコストパフォーマンスを重視する傾向があるとされます。急激な不況や大災害の経験から、「日常はいつ崩れてもおかしくない」という価値観を持つさとり世代にとっては、高級志向はあまり魅力的に映らないのかもしれません。上述した現実主義が、消費行動にも表れている、と言い換えることもできるでしょう。
デジタルネイティブ
さとり世代は、幼少からPCや携帯電話、後にはスマートフォンの普及が進んだ世代に生まれており、デジタル機器の利用やインターネットの活用に抵抗がないと言われています。情報収集が容易な環境で育ったことから、まずは何事も調べてから、という行動様式の人も多いようです。また個人差はありますが、SNS等を介した情報の発信や、得た情報の信頼性の検証に関しては比較的慎重な傾向がみられます。
さとり世代に適した指導方法
具体的に指示をする
上司や管理職、あるいはメンターとして「さとり世代的」な性格の強い社員に指導を行う場合、まずは具体的に指示を出すことが有効です。それぞれの業務について最終的なゴールの形を提示するのはもちろん、その過程で必須となるプロセスや、副次的に達成してほしいタスクがある場合は、はっきりと伝えておきましょう。「なぜそのプロセスが重要なのか」「どこまでが当人に期待されている仕事か」を示し、成果物を明確にしたうえで責任感を持ってもらうことが肝要です。
意見を尊重し主体性を重んじる
さとり世代の社員は、与えられた業務に対して盲目的に打ち込むのではなく、一歩引いた「自分の見解や意見」を持っている傾向にあります。一方で、新たな方法論の提案が受け入れられるという期待感が薄いためか、上司や周囲に対してあえて表明しないケースもあるようです。そのような場合、定期的な1on1ミーティングなどで無理のない程度に自己開示をうながす機会を設け、主体性を発揮しやすい環境を整えることで、業務効率やエンゲージメントの向上につながるでしょう。
結果よりプロセスを評価する
上記と関連して、評価の重心を成果や結果だけではなくプロセスに置くことも、さとり世代の社員にとって好意的に捉えられるポイントかもしれません。当人に「業務で出した成果はあくまで企業が求めるものであり、自己実現ではない」という意識がある場合、最低限の成果は残すものの、それ以上の成果を出すことに意義を感じにくい可能性があります。したがって、その成果を得るために工夫したプロセスや、効率化につながったポイントも評価点として含めることで、自社への信頼やエンゲージメントを高めることができるでしょう。
まとめ
理想を追うよりも現実主義で、過大な期待や夢、上昇志向といったものに執着しない「さとり世代」に対しては、企業側から自己開示の機会を設けるほか、プロセス重視の指導・評価が有効なようです。少なくともキャリアの初期段階においては、「100を200にする」よりも、デジタル適性や情報収集能力を最大限発揮してもらいながら、「100を効率よく達成する」ような活躍を求めるほうが、この世代の持っているとされる傾向に合致する可能性が高いでしょう。