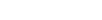ソフトスキルとは、コミュニケーション力や協調性、柔軟性、誠実さなど、人間関係や対応力に関わる非技術的能力を指します。これらは職場での信頼構築や円滑な業務推進に不可欠であり、チームの成果向上にも貢献します。日々の対話や自己反省、多様な人との関わりを通じて鍛えることが可能です。今回は、ソフトスキルの具体例や身につけるメリット、実践的な鍛え方について解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>ソフトスキルとは?
ソフトスキルの具体例
「ソフトスキル」に含まれる能力は、非常に多岐にわたります。具体例としては「コミュニケーション力・協調性・リーダーシップ・柔軟性・問題解決力」といった能力が挙げられ、これらは性格や資質といった「個人の経験」から培われる定性的な要素を多分に含んでいるのが特徴です。場合によっては「学習意欲」「自己管理能力」など、より内面的な要素を含む場合もあります。
これらの抽象的な要素があえて「ソフトスキル」と呼ばれているのは、これらの性格・資質が「仕事をする上で土台となり、ひいては良い成果を生み出すために重要な技能の一種である」という解釈が、広く受け入れられたためと考えられます。
ハードスキルとの違い
「ソフトスキル」と対をなす概念として「ハードスキル」があります。ハードスキルは仕事に直接用いる「専門知識」「資格」「技術」といった能力を表し、ソフトスキルと比べて定量的な評価が容易な傾向にあります。履歴書や職務経歴書といった、書類選考に用いられる一般的な書式で「資格欄」が普及していることからもわかるように、企業の採用活動における人材を評価する指標としては、長らくこのハードスキルが重視されてきました。
ソフトスキルが重要とされる背景
近年、ソフトスキルが重視されるようになった背景としては、主に「人材の流動化」「AIの高性能化と普及」の2点が挙げられます。
「働き方改革」やグローバル化といった外部要因により、従来型の年功序列から個人の能力重視へと企業の人材ニーズが変化する中で、人事評価のみならず採用活動においても、ハードスキルだけでなくソフトスキルに着目する企業が増えてきました。そのため、いわゆる「つぶしの利く」人材になるためには、求職者側もソフトスキルの向上を視野に入れる必要性が生じたと考えられます。
そして、さまざまなハードスキルを代替可能なまでにAI技術が進歩したことも、ソフトスキルが注目を集める要因のひとつです。特に「知識」「技術」については、チャットボットによる自動化やIoT機器による工場の機械化など、ハードスキルを習得した人材を上回る効率を獲得するケースも散見されます。
これらの要因にワークライフバランスの考え方が一般化したことも重なり、多様なキャリアプランへの応用や価値創出への貢献が見込まれる、ソフトスキルが評価される傾向が強まったと考えられるのです。
ソフトスキルを身に着けるメリット
スキルの適用範囲が幅広い
ソフトスキルは、専門分野に特化したハードスキルとは異なり、適用可能な業務が広範であることがメリットのひとつです。部署の異動や上司・同僚の入れ替わりはもちろんのこと、所属する企業が変わったとしてもソフトスキルは多くの場面で効果を発揮するため、スキルとして身につけてしまえば業界・業種を問わない活用が期待できます。
チームやプロジェクトにも影響がおよぶ
ソフトスキルの習得によって、自身と関わる同僚・上司といったチームメンバー全体との相互作用を円滑にする効果が期待できます。そのため、先述したように自己の内面に関わるスキルでありながら、プロジェクトの全体の速度感や完成度に貢献できる可能性をもったスキルです。基本的に自身が行う業務のスピードや完成度に対して重点的に影響が及ぶハードスキルの習熟度とは、この点で対照的といえるでしょう。
キャリアアップにつながる
ソフトスキルは性質としてはハードスキルと対照的でありつつも、自己研鑽が必要なスキルであることは共通しており、上述の通り、ハードスキルと同様に成果につながる可能性のある技能です。また昨今のキャリア形成においては、数値目標の達成度といった定量的な人事評価以外にも「360度評価」などの定性的な評価制度が採用されるケースもみられます。そのためソフトスキルの習熟は、ハードスキルのそれに劣らず、キャリアアップの大きな助けになるといえるでしょう。
ソフトスキルを実践的に鍛える方法
積極的な自己分析とフィードバックの活用
ソフトスキルを磨くためには、他者との関わり方に加え、自身の行動様式を見つめ直す必要があります。そのため、ある種抽象的な「どのような行動原理に基づいてその言動を取ったか?」「何が良い(悪い)結果につながったのか?」というような問いを立て、具体性を持たせたうえでフィードバックする作業を日々、自分自身に課すこととなるでしょう。
また、ソフトスキルの「棚卸し」の際には、強み・弱みといった自己分析で頻出する要素はもちろんのこと、振る舞いやコミュニケーションの癖といった、普段は意識することのない部分にも目を向ける必要が出てきます。総じてより深い、より日常的な自己分析が要求される学びの形態といえるでしょう。
継続的な学びによるインプット
このような学習をさらに効率的に行うには、やはり書籍などの情報源から継続的に知識・ノウハウを習得することが近道です。ソフトスキルでは特に自身の視点のみならず、相手方や第三者から見たときにどう感じるか、という視点を意識することが重要となります。そのため、短いスパンで情報を取り入れ「特定の価値観のみに凝り固まらない」ことを意識しながら、上述の日常的なフィードバックを行うとよいでしょう。
ロールモデルを参考にする
あるいは、書籍などの媒体ではなくソフトスキルの習得・発揮がうまくいっている他者を「ロールモデル」として参考にする、という方法も一案です。ロールモデルとして適任なのは、いわゆる「慕われる」ような、エンゲージメントの向上に貢献している上司などが考えられます。コミュニケーションの方法や問題解決に際してのアプローチ角度など、ソフトスキルをどのようにマネジメントに役立てているかを、普段とは異なる観点から観察してみるのもよいかもしれません。
まとめ
ソフトスキルは「コミュニケーション力」「誠実さ」など、一見すると個人の内面に立脚する抽象的な概念に思えますが、鍛えることで自身の業務に留まらない広範な活用が期待でき、また日々のインプットとフィードバックにより成長させることが可能な、れっきとした「技能」といえます。不確実性の高い現代社会においてはハードスキルに劣らず活用の見込めるスキルですので、概念を理解し、意識して伸ばすことでキャリアアップにもプラスに働くでしょう。