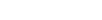不当解雇とは、客観的かつ合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇を指します。正当解雇は能力不足や経営上の必要性など明確な根拠がありますが、不当解雇は法律上無効と判断される可能性があります。企業が対応するには、就業規則に沿った手続きや改善指導の実施、証拠の整備が不可欠です。紛争時には労働局や専門家に相談することが重要です。今回は、不当解雇の定義や正当解雇との違い、企業の対応方法などについて解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>不当解雇とは?
合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇
不当解雇とは、客観的かつ合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇を指します。我が国日本においては、企業に使用される労働者は労働関連法規などで手厚く保護されているため、企業の一方的な都合で簡単に解雇することはできません。具体的には、30日以内の解雇予告通知もしくは解雇予告手当の支給などが定められており、正当な手順に従わない解雇は不当解雇と見なされペナルティの対象となります。労働者から不当解雇を主張された企業は、法的な罰則を受けるだけでなく、社会的信用の失墜も免れません。そのため、企業が何らかの理由で労働者を解雇する場合、十分注意して所定の手続きを取る必要があります。
不当解雇以外の3つの解雇
そもそも解雇は、「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」の3種類に分類できます。普通解雇は、労働者の能力不足や適性欠如、勤怠不良、私傷病などに起因する解雇です。雇用期間に定めのない労働者を解雇する場合は、合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる必要があります。雇用期間に定めがある場合であっても、やむを得ない事由がなければなりません。懲戒解雇は、企業の秩序を乱す行為に対し、懲戒処分として行われる解雇です。客観的かつ合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は、職権の濫用と見なされ無効となります。最後の整理解雇は、経営の悪化など、人員削減の必要性に基づき労働者を解雇することです。ただし、経営が悪化したからといって、一方的に解雇できるわけではありません。整理解雇を実行する場合、企業は労働契約法に基づき過去の判例でも示された4つの要件を満たす必要があります。
会社が不当解雇を行った場合のリスク
解雇は労働者の生活を左右する重大な行為でもあるため、我が国日本では労働関係法規で厳しく制限されています。労働者に不当解雇を主張された場合、企業はさまざまなリスクに晒されるため、十分注意が必要です。具体的には、損害賠償や未払い賃金の請求、当該労働者の地位確認や職場への復職など、金銭的・非金銭的な損失を被る可能性があります。また、高度情報化社会の昨今、不当解雇の事実が公に知れ渡ると、企業の信頼や評判も失墜してしまうかもしれません。信頼や評判が失墜すると、人材の流出や機会の損失、事業活動の停滞などさまざまなリスクが生じ、企業価値が低下する恐れもあります。
正当解雇との違いや不当解雇に該当する条件
能力不足や成績不良を理由とした解雇の場合
新卒社員や未経験社員を能力不足や成績不良で解雇するようなケースでは、十分な指導をしないまま能力不足と判断して一方的に解雇する行為は、不当解雇と見なされるため注意が必要です。一方、十分指導をしたにもかかわらず改善が見られないような場合は、正当解雇と認められる可能性があります。対して、経験者採用の中途社員の場合は、能力不足や成績不良に起因する解雇であっても、正当解雇と認められるケースが多いようです。そもそも、経験者採用の中途社員は、即戦力が期待されます。そのため、採用の前提となった能力が明らかに期待を下回る場合は、会社の指導が十分でなくても正当解雇と認められる可能性が高いようです。ただし、成績不良の評価に合理性がない場合は、不当解雇と見なされる恐れがあります。
勤怠不良を理由とした解雇の場合
度重なる遅刻や欠勤など、勤怠不良を理由とした解雇の場合であっても、不当解雇と見なされるケースがあります。具体的には、遅刻や欠勤に対し、特段の指導もしないまま一方的に解雇を言い渡す行為は、不当解雇と見なされる可能性があります。逆に、適切な指導を行ったにもかかわらず、遅刻や欠勤が続くような場合は、正当解雇と認められる可能性が高いようです。正当な指導や命令に従わず、今後も従う姿勢が見られず改善が期待できないような場合も、正当解雇と認められます。
転勤拒否を理由とした解雇の場合
企業に使用される労働者は合理的な理由がない場合、業務上必要な転勤命令を拒むことはできません。逆に、障害のある親族を当該労働者が介護しているケースなど、転勤はきわめて困難な事由がある場合は、転勤拒否を理由とした解雇であっても不当解雇と見なされる可能性があります。また、業務上の必要性がなく、退職勧奨を意図した転勤命令の場合は、転勤拒否が理由の解雇でも不当解雇と見なされるため注意が必要です。一方、会社が十分配慮しているにもかかわらず転勤を拒否するような場合は、転勤拒否を理由に解雇しても正当解雇と認められます。
人員整理を理由とした解雇の場合
前述の通り、人員整理を理由とした解雇を実行する場合は、企業は次の4つの要件を満たす必要があります。具体的には、企業は「人員整理の必要性」「解雇回避の努力義務」「人選の合理性」「手続きの妥当性」の4つの要件をすべて満たさなければなりません。例えば、経営上の努力を重ねても、人員整理以外に経営再建の手立てがないようなケースは、正当解雇と認められる可能性があります。逆に、合理性がなく労使間の協議も十分ではない一方的な人員整理は、不当解雇と見なされる恐れがあるため注意が必要です。
不当解雇を防ぐ企業の対応方法
就業規則に従い適切な手順を踏む
解雇の事由は絶対的必要記載事項に該当するため、企業は解雇事由を就業規則に定めておかなければなりません。不当解雇に該当するかどうかは、就業規則に定められた解雇事由に該当するか否かで判断されます。ただし、解雇事由に該当する場合であっても、一方的な即時解雇は無効です。解雇は労働者への影響が大きいため、企業には解雇予告が義務付けられています。労働者を解雇する場合、企業は30日前までに解雇予告通知を行うか、解雇予告の代わりに解雇予告手当を支給する必要があります。
配置転換や改善指導を実施する
企業の一方的な解雇は、不正解雇と見なされる可能性があります。例えば適性の欠如や能力の不足を理由に労働者を解雇するような場合であっても、企業は丁寧な指導や十分な配慮を尽くさなければなりません。具体的には、労働者の適正にあった部署・部門に配置転換を行ったり、労働者が遺憾なく能力を発揮できるよう改善指導を実施したりする配慮が必要です。配慮や指導を尽くしても改善が見られないような場合は、解雇しても不当解雇とは見なされにくくなります。
証拠を集めて退職勧奨を行う
労働者に非がある場合であっても、企業が一方的に解雇する行為は不正解雇と見なされる恐れがあります。労働者を解雇する場合はいきなり解雇するのではなく、事前に退職勧奨を行うことが重要です。退職勧奨とは、労働者が自発的に退職するよう、退職を働きかける行為を指します。労働者の納得を得やすいよう、退職金の支給や転職のサポートなどを提案する方法もあります。また、労働者に不当解雇を主張されないよう、客観的な証拠を集めておくことも大切です。
まとめ
今回は不当解雇について解説しました。不当解雇とは、合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇です。企業の一方的な解雇は、不当解雇と見なされる可能性があります。不当解雇を行うと法的な罰則を受けるだけでなく、社会的信用の失墜も免れません。労働者を解雇する場合は配慮を尽くし、適切な手順に従って実行することが重要です。