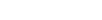労働基準法では、法定休日について「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定しています。したがって、法定休日のルールに則れば最長で12連勤までは認められています。しかし、変形休日制をとる企業の場合は例外的に13連勤以上も可能になります。今回は、労働基準法で定める連続勤務の上限や勤務間インターバルの必要性、連続勤務の注意点について解説していきます。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>労働基準法で定める連続勤務の上限
労働基準法により、使用者は労働者に対して毎週少なくても1回の休日、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えることが義務付けられています。このように労働基準法で定められた法定休日をもとにして、労働者の連続勤務日数の上限が決まります。また連続勤務日数の上限は、変形休日制・変形労働時間制かどうかによっても変わるので注意が必要です。
なお、労働基準法は、正社員など雇用形態に関係なく、日本国内すべての労働者(国家公務員の一部を除く)に適用されます。
連続勤務日数の上限は最大12日間
連続勤務日数の上限は、原則的に週1日の法定休日を設けることを基準として割り出されます。毎週少なくても1回の休日を与えるという規定ですが、1週間の起算日によって最大で12日間連続勤務が可能になります。例えば、1週間の起算日を日曜日とし、日曜日を休日とした場合、月曜日から翌週の金曜日まで連続勤務が可能になり、この場合は12日間の連続勤務であっても違法にはなりません。とはいえ法律上問題はなくても、労働者の安全と健康の確保が必要です。最大でも6日間までの連続勤務にしておく方が良いでしょう。
変形休日制における連続勤務日数の上限
変形休日制を用いる際は、限定された4週間の中で4日以上の休日を設ける必要があります。そして、その旨を事前に労働者に明示しなければなりません。理論上、1か月の1~4日を法定休日とし、4週間の残り24日を勤務日として連勤させ、さらに翌月も24連勤し、翌日から4日休む場合を考えてみましょう。こうすることで、それぞれの4週間のうち4日の法定休日という条件はいちおう形式的には満たされるため、最大で48連勤させることが可能となります。とはいえ、単に法律上問題ないというだけにすぎず、48日連続勤務の後の残りの4日間に休日を集中させるのは、労働者への配慮に欠けるため現実的ではありません。
連続勤務時間について
「1週間当たり40時間まで」「1日当たり8時間まで」と上限が規定されているとはいえ、6時間を超える労働の場合は、使用者は労働者に対して休憩を与えなければなりません。労働時間が6~8時間であれば「45分以上」、8時間を超えるのであれば「60分以上」の休憩を設けます。休憩中は労働から解放されている必要があるため、休憩中に電話番や来客対応を任せる行為は違法です。
変形労働時間制での連続勤務時間・日数の上限
変形労働時間制は、月単位・年単位で労働時間を柔軟に調整できる制度のため、期間内であれば週40時間、あるいは1日8時間以上労働時間が発生しても、残業代を支払う義務はありません。会社側にとっては、閑散期と繁忙期で労働時間を調整できる、残業時間・残業代の削減につながるなどのメリットがあります。ただし、変形労働時間制を導入する場合は使用者が一方的に就労規則等で定めることはできず、労使協定の締結や労働基準監督署への届出を行わなければなりません。また、原則として満18歳未満の年少者は変形労働時間制の対象にはできません。
1日ごとの労働時間の上限は、変形労働時間を計算する期間により異なります。1週間単位の変形労働時間制の場合は、週の労働時間が法定時間以内におさまる限り、1日10時間まで労働させることができます。
1か月単位の変形労働時間制の場合は、1か月以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内である場合には、1週40時間・1日8時間を超えて労働させることができます。
1年単位の変形労働時間制では、1ヶ月超から1年以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内であれば、特定の日や週に1日8時間・1週40時間を超えて労働させることができます。労働時間の上限は、原則として1日10時間・1週52時間です。連続して労働させることができる日数は6日、期間内の所定労働日数の上限は1年で280日になります。
関連記事:
勤務間インターバルの必要性
労働時間等設定改善法に基づき、平成31年4月1日より「勤務間インターバル制度」が施行されました。遵守しなくても罰金が発生することがない努力義務とはいえ、労働者の健康を考えると、必要性は高いといえるでしょう。
勤務間インターバルの概念
労働者の生活時間や睡眠時間を確保することを目的として、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けるシステムです。一定時間以上とは、EUのルールに基づいて「11時間以上」が理想とされています。会社は、「インターバル期間を就業規則に明示する」「ノー残業デーを設ける」「消灯時間を設定して強制的に退勤させる」などの取り組みを実施する必要があります。
勤務間インターバル導入のメリット
勤務間インターバルの導入は、業務の効率化や残業時間の縮減につながります。また、この制度の導入によって、会社のイメージアップを図ることが可能です。さらに、導入する際に政府に申請をすれば、目標時間の達成状況に応じて助成金を支給してもらえるため、比較的取り入れやすい制度といえるでしょう。
連続勤務の注意点
過度な連続勤務は労働者の健康だけでなく、会社にも悪影響を及ぼします。重大な事故を引き起こさないためにも、使用者は細心の注意を払う必要があります。
労働者に与える影響
過労による身体への影響は脳と心臓に出やすく、脳梗塞やくも膜下出血、心筋梗塞などを発症する可能性があります。また、うつ病などの精神疾患を患うことも少なくありません。睡眠不足や過労は、居眠り運転や風呂場での事故の原因にもなるため、命の危険をもはらんでいます。
会社に与える影響
連続勤務は、労働者の疲労によって集中力やモチベーションが低下し、生産性の低下を招いてしまいます。万が一、労働者の健康に著しい悪影響を及ぼし、労働災害が認められた場合は多額の慰謝料を、労働者が過労による事故を起こしてしまった場合は損害賠償を請求されます。人件費を削減しようとするつもりが、かえって多大な不利益を被る可能性があるため、過度な連続勤務は極力避けなければなりません。
2023年施行の労働基準法改正
2023年4月1日に労働基準法改正が予定されており、企業においては検討や準備が必要です。主な内容は以下の2点です。
中小企業も法定外労働における月60時間以上の割増率が50%に
労働基準法では、週40時間・1日8時間を超える労働時間については法定外労働時間として、通常の賃金より25%割増で支払うことが規定されています。加えて、残業時間が月60時間を超える賃金については50%以上の割増が規定されていますが、中小企業に対しては免除されていました。しかし、2023年4月1日からは免除が廃止され、企業規模を問わず月60時間を超える労働時間に対する賃金の割増率が50%に統一されます。ただし、労使協定を締結することにより、法定割増賃金率の引き上げ分(25%から50%への上昇の差25%)について有給休暇として付与することもできます。割増賃金率の引き上げに伴い、就業規則の変更も必要になる場合があるので確認が必要です。
賃金のデジタルマネー支払いが可能に
近年におけるキャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化により、労働者の給与受取にデジタルマネーを活用するニーズが生まれています。今回の法改正により、労働者の同意とともに一定の要件を満たすことで、厚生労働大臣に指定された業者への資金移動による、賃金のデジタルマネーによる支払いが可能になります。
まとめ
労働基準法における連続勤務の上限はあくまでも目安です。規定に従えば問題ないというわけではなく、業務内容と労働者の健康に及ぼす影響を照らし合わせて調整する必要があります。連続勤務は短めに設定し、過度なものは避けるように心がけましょう。