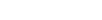働き方改革を実現する手段の一つとして、労働者が各労働日の始業と終業の時刻を自分で決め、効率的に働くことのできる「フレックスタイム制」があります。
フレックスタイム制を導入するためには、就業規則への規定や労使協定の締結、労働時間の適切な管理等が必要です。
今回は、フレックスタイム制の仕組みや導入方法、フレックスタイム制を導入するにあたっての注意点について解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、3ヶ月以内の一定期間における総労働時間をあらかじめ定め、労働者がその総労働時間の範囲内で各労働日の始業と終業の時刻を自主的に決定できる制度のことをいいます。
フレックスタイム制を導入することで、労働者は1日の勤務時間を自由に配分することができるようになり、仕事と生活の調和を図ったり、効率的に働いたりすることが可能となります。また、1ヶ月の総労働時間を満たしていれば、業務のない日は早く退勤するなど、業務の繁閑に応じて勤務時間の調整をすることもできるので、残業時間を削減する効果も得られます。
実際に、フレックスタイム制を導入することで残業時間をピーク時から6割削減した企業もあるなど、働き方改革が求められている現在において、フレックスタイム制は高く注目を集めている取組だといえます。
コアタイムとフレキシブルタイム
フレックスタイム制を導入している企業の多くは、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯である「コアタイム」と、一定の時間帯の中でいつ出社または退社してもよい時間帯である「フレキシブルタイム」とに分けています。
コアタイムの仕組みを取り入れることで、会議や外部とのやりとりがある場合に時間の設定がしやすくなるなど、フレックスタイム制の導入により業務に支障が出ることを防ぐことができます。
コアタイムの設置は義務ではないため、各企業の実情に応じて、すべての時間をフレキシブルタイムとすることも可能です。なお、コアタイムがほとんどでフレキシブルタイムが極端に短い場合などは、労働者が始業や終業の時刻を自主的に決定したとはいえないことから、フレックスタイム制とはみなされない点に注意が必要です。
また、始業時刻か終業時刻のどちらか一方のみを労働者の決定に委ねた場合も、フレックスタイム制とはみなされません。
関連記事:
フレックスタイム制の導入手続き
フレックスタイム制を導入するにあたっては、就業規則でフレックスタイム制の導入について規定するとともに、労使協定において制度の基本的な枠組みを定めることが必要です。
就業規則への規定
フレックスタイム制を導入する際には、就業規則などにより、「始業及び終業の時刻を労働者に委ねる」という旨を規定しなければなりません。その際、始業時刻と終業時刻の両方を労働者に決定させる必要があることに注意が必要です。
就業規則の作成方法については、下記のURLからダウンロードできる「お役立ち資料」で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
参考記事:
労使協定の締結
フレックスタイム制の基本的な枠組みは、労使協定で定めることが必要です。労使協定は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合と、ない場合には労働者の過半数を代表する者と締結します。
労使協定で定めるべき事項は、下記のとおりです。
対象となる労働者の範囲
フレックスタイム制を適用する労働者の範囲を定めます。すべての労働者が適用対象とされる必要はなく、個人や課、グループごとなど特定の労働者のみを適用対象とすることも可能です。適用範囲については労使でよく話し合ったうえで、労使協定において明確に定めるようにしましょう。
清算期間・起算日
フレックスタイム制では、3ヶ月以内の一定期間における総労働時間をあらかじめ定めますが、この期間のことを「清算期間」といいます。清算期間は、3ヶ月以内であれば1週間単位など任意に設定することも可能ですが、賃金計算期間と合わせて1ヶ月とすることが一般的です。
清算期間を定める際には、「毎月1日」など清算期間の起算日も併せて定めることで、どの期間が清算期間なのかを明確にすることが必要です。
清算期間における総労働時間
労働者が清算期間内において労働すべき総労働時間を定めることも必要です。総労働時間は、清算期間を平均して算出される1週間の労働時間が、法定労働時間(原則40時間)の範囲内となるように定めなければなりません。
標準となる1日の労働時間
年次有給休暇を取得した際に、それを何時間分の労働として計算するかを明確にしておくため、「標準となる1日の労働時間」を定めておくことも必要です。フレックスタイム制の対象となる労働者が年次有給休暇を取得した際には、標準となる1日の労働時間分だけ労働したものとして取り扱うこととなります。
コアタイムとフレキシブルタイム
コアタイムを設ける場合には、労使協定で開始と終了の時刻を定めることが必要です。また、フレキシブルタイムとして労働できる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始と終了の時刻も定めます。
フレックスタイム制の導入にあたっての注意点
フレックスタイム制を導入するにあたっては、下記の点に注意が必要です。特に労働時間の取扱いについては、割増賃金の支払いにも関わってくることから、しっかりと制度を把握しておく必要があります。
労働時間の算定について
フレックスタイム制では、始業と終業の時刻が労働者の決定に委ねられますが、その場合においても企業は労働者の労働時間を把握する責務を有しています。それぞれの労働者の各日の労働時間を把握したうえで、適切に賃金の清算を行うことが必要です。
労働時間の過不足について
清算期間内における総労働時間に対して、実際の労働時間に過不足が生じた場合、基本的には清算期間内で労働時間と賃金を清算することが望まれます。実労働時間の過不足を次の清算期間に繰り越すことの可否は、下記のとおり、ケースにより異なります。
実際の労働時間が過剰だった場合
この場合、過剰となった時間分の賃金を清算期間内で清算することが必要です。過剰となった時間分を、次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することはできません。
実際の労働時間に不足があった場合
この場合、2種類の対処方法が考えられます。
1つめは、規定の総労働時間分の賃金を支払ったうえで、それに達しない時間分を次の清算期間の総労働時間に繰り越して清算するという方法です。この場合、次の清算期間の総労働時間が、法定労働時間の総枠の範囲を超えてはならないという点に注意が必要です。
2つめは、規定の総労働時間に達しなかった時間分の賃金をカットするという方法です。この場合は、清算期間内で労働時間と賃金の清算が完了することになります。
時間外労働について
フレックスタイム制において「時間外労働」となるのは、通常の1日(8時間)や1週間(40時間)単位ではなく、清算期間における法定労働時間を超えた部分です。清算期間内の労働時間を通算し、それが法定労働時間(清算期間の暦日数/7[日]×40[時間]で算出)を超えている場合は、時間外労働として割増賃金の支払いが必要となります。
また、清算期間内のいずれかの月において、終了時に週平均50時間を超えている場合にも、超過分の時間外労働について割増賃金が発生します。
36協定(時間外・休日労働に関する協定)についても、1日の延長時間については協定する必要がなく、「清算期間を通算しての延長時間」と「1年間での延長時間」の協定をすれば足りることとなります。
フレックスタイム制の適用除外
満18歳未満の年少者については、労働基準法の規定により、フレックスタイム制は適用されないこととされています。
まとめ
フレックスタイム制を導入することで、労働者のワークライフバランスの実現や残業時間の削減といった効果が得られます。制度の内容や必要な手続き等をしっかりと把握したうえで、貴社においてもぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。