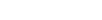所定労働時間とは、雇用契約で定められた労働者の労働時間のことです。労働者の賃金は所定労働時間を働くことによって発生します。しかし、労働時間が所定労働時間に満たない場合はどのように賃金を支払えばよいのでしょうか?今回は所定労働時間の定義や法定労働時間との違い、労働時間が所定労働時間に満たない場合の賃金の計算方法、勤怠控除の注意点について解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>所定労働時間とはどういったもの?
所定労働時間とは
所定労働時間とは、雇用契約で定められた労働者が働くべきとされている時間のことをいいます。所定労働時間には休憩時間は含まれません。つまり、始業時間が8:00、終業時間が17:00で休憩を1時間取る場合、所定労働時間は8時間となります。
法定労働時間との違い
法定労働時間とは、法律によって定められた労働時間の限度のことです。労働時間については、労働基準法第32条にて以下のように定められています。
- 第1項:使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
- 第2項:使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
この法律は、「原則として所定労働時間は、法定労働時間を超える時間を定めることはできない」と言い換えることができます。例えば、所定労働時間を1日6時間にすることはできても、1日9時間とすることはできませんし、同様に、1週間の所定労働時間を30時間することはできても、50時間にすることはできません。変形労働時間制やフレックスタイム制などの例外はあるものの、所定労働時間は、基本的に1日8時間、1週間40時間を超えない範囲で定めなければならないということになります。
残業の考え方も整理しよう
残業時間を計算する際に気を付けたいのが「法定時間外残業」と「法定時間内残業」の違いです。
一般的に「残業」と呼ばれる労働時間には、法定労働時間を超える「法定時間外残業」と、法定労働時間を超えない「法定時間内残業」があります。法定時間外残業の場合は、労働者に対し、雇用契約で定められた時間を超えた労働を課すことになるため、36協定の締結や、残業時間の限度規制、割増賃金の支払いなどを遵守しなければなりません。一方で、法定時間内残業の場合は、残業であっても雇用側に割増賃金を支払う法的義務は発生しません。そのため通常の賃金と同様に計算することになります。
例えば、雇用契約で所定労働時間を6時間と定めている労働者が、3時間の残業をしたとします。この場合、3時間の残業時間の内、法定労働時間の8時間を超えない2時間までが「法定時間内残業」となり、超える1時間が「法定時間外残業」となります。つまりこの場合、3時間残業をしても、割増賃金の支払い対象になるのは1時間分だけということです。法定労働時間を超えない限り、割増賃金を支払う義務は生じないことを覚えておきましょう。
所定労働時間に満たない場合の賃金計算方法
労務の提供と賃金の支払いには、「ノーワーク・ノーペイ」の原則が適用されます。つまり、労働の提供がなかった時間に対して賃金を支払う必要はないのです。欠勤や遅刻、早退など労働していない時間の控除はどのように計算すれば良いのでしょうか。
欠勤した場合
欠勤を控除するためには、1日あたりの賃金を算出する必要があります。計算方法は以下の4つです。
- 月給与額÷年平均の月所定労働日数×欠勤日数
- 2月給与額÷該当月の所定労働日数×欠勤日数
- 月給与額÷年の暦日数×欠勤日数
- 月給与額÷該当月の暦日数×欠勤日数
この計算方法では、控除金額が一定になるため欠勤日数をかけるだけで金額を算出できるメリットがあります。一方で、この算出方法を用いることによるデメリットもあります。例えば、所定労働日数が21日の月に20日欠勤した場合、1日出勤しているにもかかわらず、給与が支払われないという矛盾が発生するのです。ただし、このような矛盾はあるものの、年間を通しての欠勤日数に対する控除額には過不足が生じないため違法にはなりません。
月ごとの労働日数で割るため、1のような矛盾が発生することはありません。一方で、月ごとの労働日数が変わるたびに控除額が変わるため、欠勤する月によっては欠勤1日当たりの単価が異なるという別の矛盾が発生します。
1年を通して控除額が同じで給与を割る分母が大きくなるため、控除額が他の算出方法に比べて小さくなります。ただし、すべての所定労働日数を欠勤した場合でも、給与が発生しまうという矛盾が生じることとなります。
暦日数は28日、29日、30日、31日と月ごとに一定ではないため、月ごとに控除金額が変動することになります。1のような矛盾が発生しない一方で、給与計算は煩雑になりがちです。
このように、欠勤控除の計算方法によって控除金額の変動が生じます。そのため、就業規則でしっかりとルールを定めておく必要があります。また、月ごとの変動をなくすためには、1年間の総労働日数を12カ月で割った「1カ月平均労働日数」を月の所定労働時間に設定しておくと便利です。
遅刻や早退の場合
遅刻や早退により所定労働時間に満たなかった場合、遅刻や早退をした時間分だけ賃金を控除します。控除は、1時間あたりの基礎賃金を算出し、控除対象の時間にかけて金額を出します。計算方法は以下の通りです。
- 遅刻早退控除額=月給与額÷1ヶ月の平均所定労働時間×遅刻や早退の時間
※1ヶ月の平均所定労働時間は、(365日-年の休日合計)×1日の所定労働時間÷12で算出します。
勤怠控除の注意点をチェックしよう
勤怠控除に該当しない場合がある
労働者が欠勤した場合でも、以下の2つのケースでは勤怠控除には該当しません。
- 有給休暇の取得
- 会社都合の休業
有給休暇を利用した場合の欠勤は勤怠控除の対象にはなりません。
会社都合の休業とは、会社側に責任のある理由によって労働者を休業させることをいいます。例えば、経営の悪化による仕事量の減少や、生産調整による工場の停止などによる休業がこのケースに該当します。この場合、会社側は労働者に対し、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。ちなみに、地震などの災害による休業やコロナ対策のための都道府県からの要請による就業制限は会社都合の休業には当たりません。混合しないように注意しましょう。
就業規則に勤怠控除について明記する
勤怠控除の金額は、その計算方法によって変動します。また、勤怠控除の対象となる場合の規定が曖昧な状態だと、労働者とのトラブルにつながる恐れがあります。欠勤や遅刻、早退時のルールについて、就業規則にしっかりと規定しておくことで、労働者とのトラブルを避けられるようにしましょう。少人数の職場などで、就業規則を作成していない場合は、労働者に対して交付する労働契約書に、勤怠控除にかんする項目を記載しておくと安心です。
各種手当の勤怠控除を検討する
会社は労働者に対し、通勤手当や家族手当、住宅手当などの各種手当を支給している場合があります。手当に関する勤怠控除については、法律上のルールは定められてはいません。そのため、企業ごとに各種手当に関する勤怠控除のルールも定めておきましょう。一般的に、通勤手当や資格手当といった、「勤務することを前提として支払われる手当」は勤怠控除の対象となる場合が多いようです。
まとめ
労働基準法には、所定労働時間を働いた労働者に対して過不足なく賃金を支払うことについては定められていますが、所定労働時間に満たなかった場合については定められていません。そのため就業規則でルールを定めておかないと、労働者とのトラブルが発生する恐れがあり、注意が必要です。また、欠勤や遅刻、早退は誰にでも起こり得るものです。そのため、どのような場合には賃金が控除されるかについて、労働者全員がきちんと理解しておく必要があるでしょう。就業規則に定めるだけではなく、労働者に対して説明の機会を設けるなどして、職場全体の共通認識にしておくことが大切です。