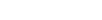労働基準法では、6時間を超えて働く労働者に対して休憩時間を与えることを義務付けています。休憩中には労働から解放されていけなければならないことや、休憩は労働時間の途中に与えなければいけないことなど、いくつかの原則があるため確認しておきましょう。今回は、労働基準法が定める休憩時間の概要や休憩時間の3原則、従業員との間に起こりやすいトラブルについて解説していきます。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>休憩時間の概要
休憩という言葉は日常的に使われていますが、労働時間の対になる意味での休憩時間は労働基準法第34条にて規定されています。当該の条文に関する通達によって、休憩時間は「労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保証された時間」と公的に定義されています。
休憩時間の最低ライン
労働基準法では、労働者がとる休憩時間の最低ラインが以下のように明記されています。
- 労働時間が6時間以内、最低休憩時間は0分
- 労働時間が6時間から8時間以内、最低休憩時間は45分
- 労働時間が8時間を超す場合、最低休憩時間は1時間
1日の労働時間は8時間までと決められているため、休憩時間は基本的には0分か45分となるはずですが、仮に8時間を超えて労働する場合、最低休憩時間は1時間とる必要があります。なお、8時間以上はどれだけ働いても最低休憩時間は変わりません。8時間を超えて労働する場合は時間外労働となりますが、時間外労働内に追加で休憩時間を与えられるよりは早く帰宅したいと思うのが労働者の心理だということから、残業の有無にかかわらず休憩時間をあらかじめ1時間と定めている企業もあります。
雇用形態による違い
いわゆるパートやアルバイトといった非正規雇用者と正規雇用者の間で休憩時間に関する規定の差はありません。したがって、例えば4、5時間程度の勤務を予定していたものの急遽労働時間を延長することになった場合、労働時間が6時間を超えれば45分の休憩時間を別途与えなくてはなりません。
AKASHIは、労働条件ごとにフレキシブルな設定が可能です。
資料ダウンロードはこちら>>
関連記事:
休憩時間の3原則
休憩は労働時間の途中に与える
上記の定義をみると、休憩時間は「労働時間の途中に置かれた」とあります。つまり、休憩は労働と労働の間に挟んで与えられるものであり、一気に労働をこなした後にまとめて与えられることはありません。例えば、午前9時から午後5時までの8時間の労働時間が終わった後に、午後5時から午後6時まで1時間の休憩をとらせても、企業は労働基準法を遵守したことにはならないということです。
休憩時間には労働から解放させないといけない
休憩時間の間は従業員に仕事をさせてはいけません。しかし、業種や職種などによっては休憩時間と労働時間を明確に分けることが難しいこともあります。例えば顧客からの電話には即座に対応しなくてはならない企業では、昼休み中でも電話の応対をする必要があるため席で待機せざるを得ません。このような場合に、果たして休憩時間と見なせるかどうかはケースバイケースです。他にも、来客対応などでやはり自由に休憩時間を使えていない場合、違法と見なされる可能性があります。労働基準法第119法により、使用者がこの義務に反した場合、30万円以下の罰金か6か月以下の懲役が科せられます。
休憩は一斉に与えなくてはならない
基本的に休憩時間は労働者が一斉にとらなくてはなりません。ただし、この原則には2つの例外が設けられています。
1つ目は特定の業種です。運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業では、この原則を順守せずとも法律違反にはなりません。
2つ目は労使協定を結んでいる場合です。労使協定においてあらかじめ一斉に休憩を与えない旨や該当する者の範囲などについて取り決めをしておくと、上記の業種以外でもこの原則を順守しなくても問題ありません。
休憩時間の分割について
最低休憩時間や、休憩に関する3つの原則を守っていれば、休憩時間をまとめて与えても、分割して与えても構いません。ただし休憩時間を分割できるとはいっても、労働者が十分に休憩できるだけの時間が確保される範囲での分割に限られるのでご注意ください。
休憩時間をめぐるトラブル
以下では、休憩時間をめぐる従業員とのトラブルの典型的な事例をご紹介します。たいていの場合、休憩時間のカウントをめぐって認識のずれが生じた結果起こるものですので、就業規則等で明確なルールを定めておくことが望まれます。
ここでは、実際にあった休憩時間をめぐるトラブルの例を基に、一つひとつの事例に焦点を当てて解説していきます。
手待ち時間中に労働機会があった場合
先にも触れましたが、電話応対のために昼休み中であっても離席できないなかで、実際に顧客から電話がかかってきてその対応をしたことで休憩時間が削られてしまった場合です。
とある企業では、12時から13時までの1時間を昼休憩としていました。しかし、昼休憩中でも電話が鳴ることがあるため、従業員に交代制で電話番をするように言い渡しており、従業員は1時間自由に休憩をとれる環境にありませんでした。後日、一部の従業員から昼休憩中の電話番は労働にあたるとして、その時間についての賃金や損害賠償の請求を求める声があがり、トラブルに発展してしまいました。
このように、電話で応対している時間を企業の側では休憩時間と認識していても、従業員が労働時間と主張し、その認識のずれからトラブルへと発展する可能性があります。このような場合は、電話応対のために使った時間はきちんと休憩時間ではなく労働時間とカウントし、別途休憩時間を付与する仕組みを作っておくのがよいでしょう。
休憩を返上して早期帰宅したい旨を従業員が申し出た場合
とある企業では「休憩を返上して働く代わりに、退社時間を早められるようにしてほしい」との声が従業員からあがりました。一見こちらは、休憩時間を勤務時の合間で取るか、最後にとるかの違いに見えます。しかし、仮に会社側がこれをよしとした場合、労働基準法違反となります。
例えば、普段は7時間勤務をする人がたまたま残業することになり、労働時間が8時間を超えたことで最低休憩時間が15分増えたとしましょう。休憩時間は労働と労働の間に与えなくてはなりませんから、残業時間中に15分の休憩を与えることになります。その際に、従業員がその休憩時間をとらなくても良いから、その分早く帰宅したいと言い出したとします。このような場合でも、企業は15分の休憩を与えなければ違法となってしまうため、必ず休憩を与えてください。
AKASHIは、労働条件ごとにフレキシブルな設定が可能です。
資料ダウンロードはこちら>>
関連記事:
まとめ
労働基準法によって規定される休憩時間についてご紹介してきました。当たり前のことですが、法律順守の基準が細かく決まっている事項はそのとおりに企業内で規定を定めるべきです。一方で、3つの原則のうちのひとつ、「一斉に休憩を与えなくてはならない」に一部例外が設けられていたように、必ずしもどの企業も同じように規定する必要はありません。そのように企業ごとに裁量が分かれている部分については労使協定などできちんと定義しておきましょう。
なお、2023年には労働基準法のさらなる改正が予定されています。
従来の労働基準法では、月60時間以下の時間外労働の場合の割増賃金率は25%、月60時間を超えると50%以上と定められていました。ただし、これは大企業にのみ適用され、中小企業には月60時間以上の時間外労働でも割増賃金率は25%以上とする猶予措置が設けられていました。
この猶予期間は2023年4月以降には撤廃され、中小企業においても月60時間以上の時間外労働に対して割増率が50%以上となるよう改正がなされます。企業は従業員の賃金と労働時間に関して、あわせて確認しておくようにしましょう。