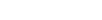レピュテーションリスクとは、企業の不祥事やSNS上の炎上などにより社会的評価が低下し、信用・売上・採用などに悪影響を及ぼすリスクを指します。原因には情報管理の不備や不適切な対応があり、企業の存続にも関わる重大なリスクです。対策としては、危機管理体制の整備や日頃からの誠実な情報発信、従業員教育が重要です。今回は、レピュテーションリスクの概要、原因や企業が取るべき予防策などについて解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>レピュテーションリスクの概要
企業・ブランドのイメージ悪化によるリスク
レピュテーションとは「評判・風評」という意味で、企業にとってネガティブな評判がもたらす、イメージダウンや風評被害といったリスクのことを指します。レピュテーションリスクが高まると、企業への信頼が失墜し、顧客離れや製品・サービス収益の低下など、企業運営にさまざまな悪影響をおよぼします。この被害が拡大すると、重大な経済的損失や廃業にまで追い込まれる可能性も考えられるでしょう。
レピュテーションリスクを意識する重要性
この現代社会において企業のレピュテーションを重視しなければならない理由の一つとして、インターネットやSNSが消費者に浸透しているという点が挙げられます。インターネットやSNSを介した口コミやレビューは、商品のヒットやサービスの認知度を上げるためのきっかけ作りになり得ます。一方で、悪評やデマなどネガティブな情報も一瞬で世界中に拡散される時代になったともとれるため、企業へのイメージや評判を企業は適切に保たなければならない時代と言えるでしょう。
オペレーショナルリスクとの違い
「オペレーショナルリスク」は、企業にとって日常的な運営や業務など、企業内部から発生したリスクを総称したものです。自然災害やヒューマンエラー、ネットワークのシステム障害などがこれに該当し、オペレーショナルリスクが保たれなくなったことで、レピュテーションリスクの誘因を招く可能性もあります。例えば、「情報漏えいによって社会的信用を失った」という一例は、情報漏えいというオペレーショナルリスクが生じた結果、社会的信用というレピュテーションリスクも次いで引き起こされた、ということになります。
レピュテーションリスクが発生する原因
生産品・サービスの品質悪化
コスト削減のために、安易に商品やサービスの品質を低下させてしまうと、企業やブランドのイメージ損失につながる最初のきっかけとなってしまいます。また仮に、企業としては品質向上を狙っていた変更だったとしても、消費者にその良さが伝わらなければ意味がありません。「前のほうがよかった」「期待したほどではなかった」という口コミが広がることになると、レピュテーションリスクが発生していると言えるでしょう。
カスタマーサポート・顧客対応のトラブル
商品やサービスそのものに問題がなかったとしても、実店舗の接客やカスタマーサポートでの対応によっては、悪い口コミが広がってしまう懸念が生じます。接客やサポート対応は消費者にとって購買体験の一環であり、その際に「不適切な対応だった」と感じさせてしまうことで、クレームや低評価の口コミが広がるケースもあります。
コンプライアンス違反
日本はここ数十年の間で情報漏えいや情報改ざん、粉飾決算などさまざまな企業の不祥事が明るみに出て、大きな問題になることも少なくありませんでした。顧客だけでなく、株主や取引先など社会全体からの信用を失う重大なレピュテーションリスクの一つであり、場合によっては経営陣の辞職など制裁が行われる可能性もあります。
風評被害
残念ながら、ネガティブな口コミやレビューは事実とは異なる内容が拡散されることもあります。悪意のあるデマの場合もあれば、勘違いや価値観の違いなどですれ違いが起こり、事実とは異なる情報が世に出てしまうこともあるでしょう。SNSでこのような情報が発信されると拡散されやすいため、風評被害として企業のイメージや信用に傷がついてしまうことも考えられます。
レピュテーションリスクへの企業が実施すべき対策
社内教育・マニュアル化の徹底
情報管理やセキュリティ対策、コンプライアンス対策などの社内教育を研修などで実施することは、リスクを減らすために有効な策の一つです。社内規範や価値観・ビジョンを従業員全体が意識することで、一人ひとりが企業に所属している一員という責任を感じて行動できるようになります。また、リスクを未然に防ぐためにも、マニュアル化できるプロセスはマニュアルを定めておくと、サービスや商品・製品の品質維持にもつなげられるでしょう。
社内監視・チェックの強化
企業内での業務プロセスが適切に行われているか、監視やチェックを強化することは、レピュテーションリスクをはじめさまざまな企業内リスクを予防するための対策です。この監視やチェック体制は、現場だけでなく役員や経営層などにも範囲を広げられるとより効果的です。企業が違反者に対してどのような制裁を下すのか、その動向によっても社会の目や印象は大きく変わるかもしれません。適切な処遇を行えるように、明確な基準を事前に設けておきましょう。
広報やブランディング発信方法の整備
企業が社会や消費者にとって一定の信頼と信用を勝ち取るためには、日ごろから正確かつスピーディーな広報活動や情報発信を実施していることが重要になります。ただし、あまりにも事実とかけ離れた誇大広告を実施すると、今度は「事実と違う」というレピュテーションリスクが発生するため、広報担当者によって情報発信の内容に乖離が生じないように内容や発信の方法を整備しましょう。
リスクそのものへの早期対応策を検討
レピュテーションリスクを予防するための対策も重要ですが、万が一リスクが発生した後のアフターフォローの策を考えることも企業にとっては重要です。ネガティブな情報が表出したとき、その後の企業の行動によってさらに信用を損なうのか、もしくは信頼回復につながるのか、その動向が決定するからです。事情説明の場を設けるためのプロセスなどをあらかじめ定めておくと安心です。
まとめ
近年、インターネットやSNSの発達により、サービスや商品のブームが生まれるなどポジティブな情報拡散が行われる反面、ネガティブな情報拡散へのリスクを企業が対処しなければならない時代になっています。リスクの予防や被害が発生したときに拡大させないためにも、日ごろから対策を考えておきましょう。