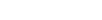リンゲルマン効果とは、集団作業において人数が増えるほど一人あたりの貢献度が低下する現象を指します。原因は責任の所在が曖昧になることで、手抜きやモチベーション低下が起こることにあります。対策としては、役割分担の明確化や成果の可視化、個人への適切な評価が効果的です。今回は、リンゲルマン効果の概要と組織での弊害、改善に向けた取り組みなどについて解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>リンゲルマン効果の概要
「社会的手抜き」とは
「リンゲルマン効果」はフランスの農学者であるマクシミリアン・リンゲルマン氏が提唱した現象で、日本語では「社会的手抜き」などといわれています。「社会的手抜き」とは、集団で作業をする際、人数が増えれば増えるほど一人あたりの貢献度やパフォーマンスが低下する現象です。リンゲルマン効果が表れる要因には、責任感の希薄化やモチベーションの低下などが挙げられます。具体的には、「自分一人が手を抜いても他のメンバーがカバーしてくれる」「自分の貢献が目立たなくなるためモチベーションが上がらない」といった、対人関係のプロセスが大きな要因となっていると考えられています。
綱引き実験の事例
集団作業において人数が増えるほど一人あたりの貢献度が低下するリンゲルマン効果は、マクシミリアン・リンゲルマン氏が1913年に実施した「綱引き実験」で発見されたそうです。綱引き実験では、一人で綱引きを行った際の作業量を100%とすると、2人・3人・4人と参加者を増やしていくと徐々に作業量が低下し、8人になると一人あたりの作業量が50%を下回るほど低下することが示されました。このように、共同作業においては人数が増えれば増えるほど責任や役割が曖昧になり、一人あたりのパフォーマンスは低下する可能性があるようです。リンゲルマン効果は「自分が頑張らなくてもどうにかなる」という意識の表れ、とも考えられます。
リンゲルマン効果による組織への影響
モチベーションの低下
組織内にリンゲルマン効果が蔓延すると、メンバーのモチベーションは低下します。そもそもリンゲルマン効果が起こりやすい大規模な組織はメンバー一人ひとりの成果が目立ちにくいため、いわゆる「手抜き」が蔓延しやすいのも問題です。「自分が頑張らなくても他のメンバーがカバーしてくれる」「たとえ頑張ったとしても正しく評価されない」という意識が、「社会的手抜き」を誘発します。モチベーションの低下は離職の引き金にもなるため、リンゲルマン効果の放置は大変危険です。まだ主体的に動けない新入社員や若手社員はリンゲルマン効果の影響を受けやすく、早期離職につながりかねないため、特に注意が必要だといわれています。
生産性の低下
リンゲルマン効果の結果モチベーションが下がると、組織の生産性は低下してしまいます。メンバー一人ひとりの手抜きはわずかな作業量だったとしても、組織全体で見ると生産性を引き下げる大きな要因となっているケースも珍しくありません。リンゲルマン効果は、知らず知らずのうちに組織内に蔓延しやすいといわれています。気付いたときには生産性が大きく低下していたという可能性もあるため、リンゲルマン効果には注意が必要です。また、組織内の手抜きが常態化すれば、優秀な人材の離職にもつながりかねません。優秀な人材が離職すると、当然ですが組織の生産性は著しく低下します。
フリーライダーの増加
リンゲルマン効果の常態化は、フリーライダーを生み出す原因にもなります。フリーライダーとは、自分ではコストや労力を負担せず、他人の私益や成果に「ただ乗り」する人です。フリーライダーが増加すると他のメンバーの負担が大きくなり、著しい不公平感が生じるという問題があります。当然周囲のモチベーションは下がるため、組織の生産性が低下してしまうのも深刻な問題です。リンゲルマン効果はフリーライダーの原因になり、「頑張っても正しく評価されない」「頑張りが給料に見合っていない」といった、ネガティブな感情を生み出す要因になります。組織内の不満が高まると優秀な人材の離職にもつながるため、組織の弱体化につながりかねない大変危険な問題です。
リンゲルマン効果を改善させるための対策
業務内容を明確にする
リンゲルマン効果は、組織内の仕組みが曖昧であるために生じるケースが多いようです。特に、仕事の範囲や責任の所在が曖昧だと、リンゲルマン効果が生じやすいといわれています。リンゲルマン効果を防ぐには、「誰が」「いつまでに」「なにを」といった、いわゆる「業務体」を明確にすることが非常に効果的です。業務範囲と役割分担を明確にすることで、手抜きや無駄、作業の重複などを未然に防ぐことができます。集団の成果を評価するような業務であったとしても、メンバー一人ひとりの動きに着目し、担当や責任を明確にしてこくことが重要です。
チーム編成を少なくする
綱引き実験でも示されたとおり、集団の母数が多くなれば多くなるほど、リンゲルマン効果が生じやすいといわれています。実際、1人で綱引きをしている場合の作業量と比較し、8人で綱引きを行った場合は一人あたりの作業量が半分以下に低下することが示されました。逆にいえば、母数を減らすことで、リンゲルマン効果の影響を最小限に抑えられる可能性があります。具体的には、少数精鋭主義を導入し、集団の規模を制限するのも効果的な対策です。集団の規模が小さければメンバー1人の動きや成果が可視化されるため、リンゲルマン効果も生じにくくなります。
公正な評価体制を構築する
リンゲルマン効果の蔓延を防ぐには、可視化された成果に対し、公正な評価体制を構築することも重要です。特に「自分の頑張りが正しく評価されていない」「自分が頑張らなくてもどうにかなる」というネガティブな意識は、組織に悪影響を及ぼすと考えられます。社会的手抜きともいえるリンゲルマン効果を抑止するには、メンバー一人ひとりが「自分の頑張りは正しく評価されている」と感じられるような仕組みを作り出すことが大切です。正しく評価されていると感じたメンバーはモチベーションが高まるため、生産性の向上も期待できます。
まとめ
今回はリンゲルマン効果について解説しました。リンゲルマン効果は社会的手抜きともいわれ、集団作業において人数が増えれば増えるほど一人あたりの貢献度やパフォーマンスが低下する現象です。モチベーションや生産性の低下、フリーライダーの増加を引き起こし、優秀な人材の離職にもつながります。特に母数の大きな集団で起こりやすいため、少数精鋭主義を導入するなど対策を取り、リンゲルマン効果の蔓延を防ぎましょう。