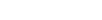【主な登場人物】
※この小説はフィクションであり、実在の人物・団体などとは一切関係ありません。 |
■scene1 ツィッター
「綿あめ屋さんみたいだなぁ」
夜と言うにはまだ早い、2015年7月の19時過ぎ。上田は土曜夕刻の渋谷の人ごみのなかで、もう何年も帰っていない故郷のお祭りの縁日を思い出していた。
ショッキングピンク、スカイブルー、レモンイエロー…。前職の会社の先輩、後藤に連れ出されたキャバクラの入り口の両脇には、色とりどりの風船で飾り立てられた花輪が何基も立っていた。それが、さまざまな色つきのビニール袋に入った綿あめをぶら下げているお祭りの屋台の遠い記憶と重なった。白色灯に照らされて絹糸のようにつやつや光るフワフワなお菓子を、リズミカルに次々とつくりだすコワモテのおじさん。子どもが見てはいけないもののような気がして、逆に時間を忘れて割り箸に綿あめがからめとっていく妙技に引きつけられた。
少し前を歩く後藤が首だけ上田の方へ回して、ひときわ目立つ花輪を右手の人差し指で指さし、口元に笑いを浮かべた。メタリックブルーのイルカの風船が揺れているその花輪には「麗華さんへ ゴーゴーより」というパネルがかけられていた。“ゴーゴー”というのは後藤のあだ名。「後藤郷太」だから“ゴーゴー”。「イケイケ、いいじゃん」。後藤も自分のあだ名を気に入っていた。
入り口の前には、小さなダイヤのピアスをしたスキンヘッドのいかつい黒服があたりを警戒するように立っていた。後藤を目にとめると愛想笑いを浮かべ、右手のひらを左胸にあててお辞儀をし、左手で入り口のドアをゆっくりと開いた。インカムのマイクに何ごとかをささやき、舌足らずの低い声で「いらっしゃいませ、後藤様」とふたりを中に促した。後藤は無言で軽くうなずきながら中に入り、後藤より少し背の高い上田がおどおどしながら後ろに続いた。
「後藤様、お越しいただきありがとうございます」
「お待ちしておりました、後藤様」
インカムで合図したのだろう、ふたりが店内に足を踏み入れると同時に客席フロアに続く10メートルほどの通路の向こうから黒服が2人現れた。ひとりは2ブロックの短髪をムースで七三に固めた背の高い黒服、もうひとりは毛先を遊ばせたチャラいロンゲの吊り目の黒服だった。
「姫は、どこかなぁ」
後藤は白い七分丈のバミューダの後ろポケットに突っ込んでいた左手をゆっくり抜き、黒服たちに向かっておどけた敬礼をしながら、上機嫌な声で言葉を区切って聞いた。
「麗華さんはこちらでお待ちです」
「素敵なお誕生祝いの花輪を頂戴し、麗華さんも喜んでいましたよ」
おべんちゃらを並べる黒服たちにエスコートされながら後藤が肩を揺すりながら進んでいく。
通路から一段下がった客席フロアは奥が広い“コの字形”。オフホワイトの革張りのソファが壁の三方をぐるりと囲んでいる。規則的な間隔で並んでいるガラステーブルを挟んだソファの向かい側には同色の大き目の四角いスツール。トランス系のBGMが流れる店のフロアのまんなかの天井に吊るされた豪勢なシャンデリアが、間接照明の光を反射させていた。
「ゴーゴーさん、ありがと~」
“コの字形”の客席フロアの奥から、後藤に向かって派手な巻き髪のキャバ嬢が黄色い声をあげて手を振る。クレープのような薄手の生地を何枚も重ねたふわふわの白いスカートに、上半身は白いチューブトップ。浅く日焼けした丸出しの肩がラメのボディスプレーでキラキラしていた。
上田はアメリカンコミックのキャラクターが大きくプリントされたグレーのTシャツと、学生時代から履き続けている膝が抜けたカーキ色のくたびれたチノパンといういつものいでたち。店の雰囲気とはあまりに不釣り合いな自分の服装に、今朝起きた人生最大のショッキングな出来事を忘れ、気まずさを感じていた。
この日の朝、上田は一緒に起業した黒野からツィッターで「会社、辞めるわ」と一方的に告げられたのだ。その理由はまったく思い当たらない。謎だった。
■scene2 星々
黒野とは大学以来の仲。プログラミングの“オタクサークル”で出会った。当時から“謎”が多かった。一方的でもあった。
サークル仲間からは、よくも悪くも、「天才」と言われていた。エンジニアとしての力量はすでにプロ級。だけど、誰かに話しかけられても、「ああ」とか「うーん」とか、いつも上の空。まともに会話が成立した試しはない。あとになって自分の考えや意見を断定口調でツィッターを通じて一方的に送りつけてくる。
「スマホを電話として使ってないし、メールなんていう面倒なものは絶対使わない」。そんな理由で誰も黒野の携帯番号やメアドは知らない。連絡手段は、学生の頃から今にいたるまで、いつもツィッター。才能にあふれ、対人コミュニケーション能力が極端に劣る紙一重の“天才”。それが黒野だった。
上田と黒野の距離が一気に縮まったのは、大学3年生の夏合宿。サークルで交流のある筑波大学の准教授の研究室の見学を兼ねて筑波山に行ったときのことだった。学生乗りの夜の宴会でほかのサークル仲間は早々に沈没し、あまり酒は得意ではない上田が酔い覚ましに露天風呂に行くと、黒野が先に湯に浸かっていた。
「おぅ」
上田は黒野に呼びかけたが、なんの反応もない。上田は黒野と微妙な距離感を保ちながら湯船に身を沈めた。
楽しいことも、そうではないこともあった大学生活、その最後の夏合宿。すぐにフラれたけど、初めて女の子とも付き合った。星空を眺めながら露天風呂につかり、とめどもない想いに浸っていると、酒が入ったこともあって、上田は感傷的な気持ちになった。
「オレの夢はITの技術で世界を幸せにすること。だから、大学を卒業したらそんな仕事がしたいんだ」
上田は唐突に、胸に秘めていた青臭い想いを口走った。
「そうか。オレも、だ」
一呼吸あって湯煙の向こうから聞こえた思いがけない返事。黒野の声だった。
いつもは「あー」とか「うーん」とかしか言わない黒野が反応したことに驚き、上田は黒野の顔を見詰めた。黒野は上田の視線を無視するかのように星空を見上げていた。
後期の授業が始まってしばらくすると、黒野から「大学、辞めるわ」。そんなツィートがあった。
学校そっちのけで黒野がクラウドソーシングでプログラミングやシステム開発の仕事をしていることを上田は知っていた。大学を辞めるというメッセージは、就職せずに自力で稼いでいくという宣言だ。「プログラミングで世界を平和に、豊かにしたい」という理想を実現するためのチャレンジを黒野は開始した。そう思うと胸が熱くなった。
「オレも力をつけたら後に続く。いつか一緒に仕事をしようぜ」
上田はそう返信した。そして、1年前、ふたりは一緒に起業した。
そんな黒野が「会社、辞めるわ」とツィートしてきた。黒野に抜けられるのは会社にとって大幅な戦力ダウン。それ以上に、これでかけがえのない夢が失われると悟った時に胸の奥に走った、じりじりとした痛みが辛かった。なんとか考え直してほしい、思いとどまってほしい。上田は黒野にツィートしまくった。返事がくることはなかった。
「今日の夜、空いてる?」。
後藤から電話があったのは、黒野にツィートすることに疲れ果て、放心して天井をぼーっと見上げていた昼近くだった。振動するスマホの画面に「発信者:後藤センパイ」と表示されているのを確認すると、上田はあわてて電話に出た。
「ちょうど自分も後藤さんに聞いてほしいことがあったんです」。
ふたりは夕方の6時30分に上田の会社の近くの桜ヶ丘のカフェで待ち合わせることにした。
後藤は前の会社の先輩。上田が起業する2年前に独立した。業績は右肩上がりで、上田の会社のような桜ヶ丘のマンションオフィスではなく、宮益坂の中ほどにある、雑居ビルではあるけど1フロアを借り切っている“イケイケ、ベンチャー”の経営者。実績、力量、知識、経験、そして人間的な魅力。どれも後藤にはかなわないと上田は思っていた。だから後藤に相談したら、一発逆転の知恵を授けてくれるかもしれない。そんな期待をしていた。
■scene3 追憶

後藤は自分で時間を指定しておきながら、いつも20~30分は悪びれることなく遅れて来る。上田は約束の時間の10分前に訪れ、すっかりぬるくなったアメリカンコーヒーをすすりながら、黒野と起業するまでのことを追憶していた。
――上田は夏休みが終わる直前、ナビ媒体で見つけた、とりたてて特徴のない大手情報通信会社傘下の中堅ソフトハウスから内定をもらった。給料は中の下くらい。大学4年間を過ごした下宿先のアパートから電車1本で通勤できるのが魅力だった。その会社にSEとして入社し、社内研修が終わり、現場に配属された頃には、露天風呂で黒野に話した青臭い想いなど、すっかり色あせていた。上田の想いに再び火をともしたのは、会社の先輩、後藤だった。
上田の下の名前は、百をふたつ重ねて「百々(もも)」。“公私ともに100%の人生を歩めるように”と母方の祖母がつけてくれた。上田は女の子のような、桃太郎のような響きが、小さい時からあまり好きではなかったが、自身は人見知りなのに、年上からも年下からも「モモちゃん」と、いつも向こうから声かけてくれ、すぐに打ち解けることができたのは、よかったと思っている。後藤も初対面のときから自分を「モモちゃん」と呼んでくれた。
後藤は4歳年上で、「数字をつくれる営業」として社内から一目置かれる存在だった。天性の明るさと人懐こさで活躍し、いつも何人かの取り巻きに囲まれている。ひたむきなだけで地味な存在の上田とは対照的な存在。そんな後藤から「モモちゃん」と親しげに呼ばれるのは、少し誇らしい気持ちがしていた。
後藤が独立したのは、上田が入社して2年後のこと。噂では、直属の上司と言い争いになり、後藤が辞表を叩きつけた、ということだった。具体的にどんな事情があったのかはわからない。そこには触れていけない雰囲気があった。しかし、若手社員の間では後藤の行動を称賛する声が圧倒的だった。後藤と言い争いになった上司というのが、粘着質かつ陰湿な性格で、若手から嫌われていたからだ。
後藤の最終出社日、ランチを食べに行った会社の近くの定食屋で偶然、上田は後藤と同じテーブルになった。辞表を出した直後は社内の若手から密かにヒーロー視されていたが、少したつと誰もその話題には触れなくなり、取り巻きも離れ、後藤は単独行動することが多くなっていた。
「おー、モモちゃん、久しぶりだな」
後藤がいつものような明るい笑顔を見せてくれたことに上田はホッとした。後藤に手招きされ、隣の席に座り、世間話をしながら、ふたりでハンバーグランチをつついた。なにがあったのか、これからどうするのか。上田は後藤に聞きたかったが、質問してはいけないような気がしていた。食べ終える頃、後藤が口を開いた。
「昔から起業したいと思っていたんだ。だから、オレは全然、後悔していないし、逆にチャンスをもらったと思っている」
「起業するって、会社をつくるんですか?」
思いがけない言葉に上田は驚いた。
「ああ。オレには会社勤めはあっていない。起業して、自分の力で夢をかなえるんだ」
自分の力で夢をかなえる―。黒野と見上げた露天風呂の星空を思い出した。色あせたはずの青臭い想いがうごめき、自分でも驚いた。
■scene4 恩人
どんな事業をするのか、起業するってどういうことなのか。後藤の言葉をきっかけに、上田は矢継ぎ早に質問した。顔が上気していく。後藤は熱い口調で上田の質問にすべて答えると、おやっという目をして上田を見た。
「もしかして、モモちゃんも起業したいって思っているの?」
大人が子どもを諭すような柔らかい口調だった。
「いや、実は…」
青臭い想いだということがバレないよう、慎重に言葉を選びながら、学生時代に黒野と一緒に起業したいと思ったことがあること、黒野は“変人”だが天才的なプログラマーであること、後藤と同じように、ふたりにもかなえたい夢があることなどを打ち明けた。
「モモちゃん、こんなケチくさい会社にいたって夢なんて実現しっこないぜ。起業は大賛成だ。でも、モモちゃんはまだ経験が浅い。もう少し仕事を覚えてから独立したほうがいい。会社なんて、利用するためにあるんだ」
上田は後藤のアドバイスに素直にうなずいた。
「よし、これからも時々会って、情報交換しよう。オレがこれから経験することは、モモちゃんの起業に役立つかもしれない」
最後に後藤からこう言われたときは、上田の漠然とした起業の想いは具体的な確信に変わった。今日から2年以内に起業とすると決めた。
後藤はSESベンチャーを起業した。後藤本人にITスキルはなく、SEを募集し、本人は仕事をとってくるトップ営業に専念した。前職でつちかった人脈を活用し、滑り出しから業績は順調だった。自分の“天性の営業センス”を活かし、ITビジネスにこだわることなく、テレアポ代行・保険代理店・携帯アクセサリー販売代理など、手広く事業を展開した。
後藤とランチをしてから間もなく、上田も自分なりの起業準備を進めた。ツィッターで黒野に連絡をとり、起業への熱い想いをメッセージし続けた。黒野はAIやIoTなどの分野で活躍するフリーのSEとして働いていた。上田は黒野のしている仕事がまぶしく感じた。最初はつれない返事しかくれなかったが、上田が本気であることを理解すると、黒野はいろんな事業提案をしてくれるようになった。
後藤とのランチから2年半が過ぎ、当初の計画より少し遅れて、上田はついに起業を果たすことができた。黒野からは現状のまま、必要があるとき以外は出社せずリモートワークすることを条件提示された。上田は喜んで受け入れた。黒野には自由に働いてもらい、独自の自社サービスの開発に専心してもらうことにした。
上田が起ち上げたのもSES会社。後藤は「がんばれよ」と励ましてくれ、仕事をいっぱい回してくれた。採用に困っていると、後藤は自分の会社からメンバーを何人か転籍させてくれた。おかげで会社は順調に立ち上がった。起業から1年がたち、メンバーは10人くらいに増えた。
しかし、利益率の悪い仕事が多く、社長の上田自身、デバッグなど現場の業務に毎日奔走していた。いつも人手不足だった。会社を始めて半年くらいたつと、月に1人、2人は辞めていく状態が続いた。採用しては誰かが辞めるから、採用活動も忙しかった。時間はいくらあっても足りなかった。
仕事の7割以上は、後藤がらみのもの。残りは前職の会社から発注してもらっているデータ入力の単純な仕事だった。要は後藤の会社の“下請け”。後藤がくしゃみをすれば上田の会社は寝込んでしまう。それでも上田は、夢の実現に向かって着実に前進している気がして、ワクワクしていた。後藤のことを、夢の実現を応援してくれる「恩人」だと思っていた。
――後藤はいつものように20分以上遅れて待ち合わせのカフェにやって来た。後藤に会った途端、黒野に去られて重く沈んでいた気持ちが軽くなるのを上田は感じた。
「後藤さん、実は―」
上田の言葉にかぶせるようにして、後藤は唐突に切り出した。
「モモちゃん、これから行きたいところがあるんだ。付き合ってくれるよね」
後藤は注文したクリームたっぷりのアイス抹茶ラテを一息に飲み干すと、上田をともなってカフェを出て、車を拾った。そして、ふたりが待ち合わせた桜ヶ丘のカフェから10分ほどタシーを走らせ、キャバクラの前に横付けさせた。
「会社、辞めるわ」第1話 おわり

【連載小説】ブルーベンチャー |
クラウド型勤怠管理システム「AKASHI」
勤怠管理システムを導入することで、効率的かつ確実に労働時間を管理することが可能となります。ソニービズネットワークス株式会社が提供するクラウド型勤怠管理システム「AKASHI」は、36協定設定、年休管理簿や労働時間の把握など、あらゆる法改正や複雑な就業ルールに対応する機能をフレキシブルに対応します。15年以上のノウハウを活かした充実のサポート体制で導入後も安心です。
今ならAKASHIのサービスを30日間無料でお試しいただける無料トライアルを実施していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。