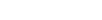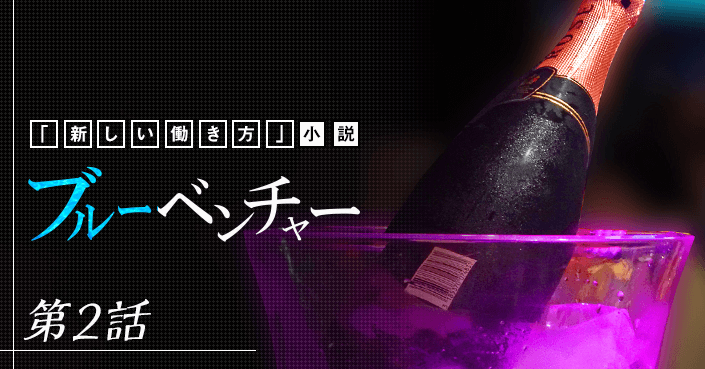
| <前回までのあらすじ>「会社、辞めるわ」 第1話
共同創業者の黒野に突然去られた上田。なにが理由か、まったく思い当たらない。会社の今後も不安になってきた。頼りにしている先輩経営者・後藤にすべてを打ち明け、相談しようと考えた。後藤は行きつけのキャバクラに上田を連れ出した。 ※この小説はフィクションであり、実在の人物・団体などとは一切関係ありません。。 |
■scene5 ピンドン
「オープンラストで指名なんて、ほんと、ありがと~」。
「麗華の誕生日だからな、しょうがねぇよな」
客席フロアのセンター奥のソファに後藤が腰かけると麗華はすぐにしなだれかかり、後藤を見詰めながら甘ったるい声で礼を言った。黒服たちと同じように、上田の存在などまったく眼中にない。
上田は後藤の真向かいのスツールに腰かけると、自分の隣に座ったキャバ嬢に小声でたずねた。
「オープンラストってなんですか?」。
「開店から閉店まで、ずっと指名しっ放し、ということよ」
麗華に比べたら地味な、しかし街中で見たら二度見するような、体にピッタリした露出度の高い花柄のワンピースを着たキャバ嬢が、「なにも知らないのね」と言わんばかりの見下したような笑みを浮かべて答えた。
「姫、誕生日、おめでとう」
後藤は、ジャケットのポケットからミント色の包み紙とシルバーのリボンでラッピングされた小さな箱を取り出し、麗華にポンッと手渡した。
「え! ホントにいいの!?」
そう言いながら麗華はさっそく包み紙を開き、目を輝かせた。
「欲しかった新作のピアス! どう、似合う?」
麗華はゴールドのピアスを耳にあて、後藤に見せる。
「質屋に売ったり、ネットで転売したりするんじゃねぇぞ」
「やな感じ~」
麗華は頬をふくらませ、怒ったような表情を見せ、後藤にからめていた腕をほどき、少し距離を置いた。
「後藤様、いかがなさいますか?」
「麗華のお誕生日だし、ドンペリじゃないと許さない~」
ロンゲの黒服がおしぼりやグラス、突き出しがわりのナッツが盛られたセットを運んできたタイミングで、ずっと側で控えていた2ブロックが後藤にオーダーを促すと、麗華は後藤を非難するように口をとがらせて混ぜ返した。
「アホか」
後藤は麗華をたしなめると、2ブロックに向かって
「ピンドン、持ってきてくれ」
「やっぱりかっこいい! ゴーゴーさん、ありがと~!」
さっきまで頬をふくらませていた麗華は、満面の笑みで後藤の腕に抱きついた。
そのとき、上田は伸びきったチノパンの後ろポケットに突っ込んでいたスマホの振動を腰に感じた。引っ張り出して画面をのぞきこむ。黒野のツィートだった。「なぜだ」「考え直してくれないか」「お前がいないと困る」という、上田が今日の午前中に必死にすがり、何度も送ったメッセージへの返信。そこには、こんな短いフレーズがあった。
「いい加減、気づけよ」
何に気づけと言うんだ?―。画面に表示された黒野のメッセージが上田の胸の奥に沈み込んでいった。
年下のキャバ嬢がタメ口で話す下世話な世間話、ゲームの敗者をはやしたてる一気のコール、歓声と嬌声―。上田は左手首にはめた安物の腕時計を眺めた。日付が変わる時間になろうとしていた。
酒はあまり強くなかったが、上田はピンク色のシャンパンはフレッシュでおいしいと感じた。そのあとに出された後藤のキープボトルは、水で薄めても喉にひっかかるいがらっぽさがあった。
ルールがよくわからない上田はゲームに参加しなかった。そのおかげで一気させられることもなく、自分のペースで飲むことができた。「いつ、後藤さんに黒野のことを切り出そうか」。タイミングをはかっていた。
「オレの可愛い後輩だから」。
いい感じで酔いが回ってきた後藤は、キャバ嬢たちに上田のことをそう紹介した。
「ゴーゴーさんって、ふだんはどんな人なの?」
ほんとうは大して関心をもっているわけではない、キャバ嬢たちのお約束の質問。
「昔から憧れの存在で、経営者としてもすごい」というようなことを上田は話した。自分も起業したが後藤さんみたいになりたいと思っている、起業のときから助けてもらい、仕事をまわしてくれている、いろんな相談に親身にのってくれる。そんな上田の話を後藤はニヤニヤしながら聞いていた。
■scene6 ピンハネ
「ふーん、ゴーゴーさんってホントはすごいんだね」
キャバ嬢たちが適当に相槌を打っていると、上田の隣に座っていたキャバ嬢がそう聞くのが当然の流れであるかのような自然な口調でたずねた。
「それで、ゴーゴーさんって、どのくらいピンハネしてるの?」
上田は不意打ちを食らったように感じた。その質問が上田に向けられたものなのか、後藤に聞いたのかわからず、上田は後藤の様子をうかがった。
後藤にしなだれかかっていた麗華が、そのキャバ嬢をにらみつける。質問したキャバ嬢はハッとした表情を浮かべた。それまで盛り上がっていた場がエアポケットに陥ったように、シーンとした。
後藤は聞こえていなかったのか、質問に答えるそぶりも見せずに2ブロックを呼びつけた。
「そろそろ、アレ、持ってきてくれ」
少しして麗華の年の数だけ赤いイチゴが飾られているデコレーションケーキが席に運び入れられた。それを合図に、場がふたたび弾けた。
閉店近くになり、ほかのキャバ嬢たちが手洗いに立っていたとき、麗華は違うテーブルに呼ばれた。上田は後藤とふたりきりになったその瞬間、思い切って切り出した。
「ゴーゴーさん、じつは黒野が辞めるって言いだして。どうしたらいいですか」
すっかり出来上がり、上機嫌の表情だった後藤の眉がぴくっと動いた。
「あー、お前んところのあの変わりモンだな。カネでモメたか?」
「いや、理由がわかんないですよ」
「前にオレんところに電話してきて、『ムチャな仕事を回すな』とか言ってきたヤツだよな」
「…あの時はすいません。でも、自分とゴーゴーさんが働いていた前の会社が未払い残業代とかで、この間、ヤラれちゃったじゃないですか。ウチもめちゃくちゃ残業は多いんですけど、そんなの払える状況じゃないし。黒野はそんなことを気にしてたらしくて」
「確かにヤラれちゃったよなぁ。アホな会社だよなぁ。オレがいたときから、アホなヤツばっかりだったけどなぁ」
「誰がヤラれたの?」
テーブルに戻ってきた麗華が話に割り込んできた。
「麗華のことを話してたんだよ」
「大切なお誕生日にシモネタ言わないで。ゴーゴーさん、ヘンタイ~」
「よぅし、じゃあ最後にピンドン…。いや、ヘンタイだからモエピンだ」
後藤が気勢を上げる。そして上田に顔を寄せて、こうつぶやいた。
「とにかく気にするな。辞めるやつは辞める。誰にも止められない。仕事なんかいくらでも回してやる。一緒に夢をつかもうぜ」。
最後の最後に後藤の掛け声で一気をさせられた上田は、後藤と別れると会社があるマンションの別フロアの自分の部屋まで、どうにか千鳥足でたどりついた。着の身着のままでベッドに倒れ込み、同じ言葉を何回もつぶやいた。
…一緒に夢をつかもうぜ。…夢をつかもう。
大学最後の夏合宿で黒野と一緒に露天風呂から見上げた星空が、頭の中に広がった。湯に浸かりながらで、黒野と自分はピンクのシャンパンを飲んでいる。星々が色とりどりの風船となって空から降ってきた。そのひとつを黒野がつかむと、今度は上昇していく。「なにも知らない」と見下すような笑みをオレに向けながら、どこまでも上昇しいく。黒野の姿がどんどん遠ざかり、米粒になり、点になり、夜空に溶け込んで、消えた。すべてが暗黒になった。
なにかが頬をくすぐっている。どのくらい眠っただろうか。ザーッという耳鳴りを不快に感じながら、重い瞼をゆっくり上げていく。目の前を小さなカニがちょこちょこと横切っていく。なんだ、頬をくすぐっていたのは、このカニだったのか…。
カニ? なんで? あわてて飛び起きる。目の前には、どこまでも青い水面が広がっていた。後ろを振りかえると幾本かの松の木立の向こうの遠くに、低層の建物が見えた。足元を見る。サラサラした砂のうえに立っていた。海だった。耳鳴りと思っていたのは穏やかな波の音。潮の香りが鼻腔のなか一杯に広がる。風で巻き上げられた砂粒が目に入り、痛みをおぼえた。
夢の続きにしては、あらゆるものがリアルすぎる。上田は入った砂粒をとろうとして目をしばたたかせながら、夕べの記憶を高速で巻き戻した。マンションの自分の部屋にたどりついてベッドに倒れ込んだことは、覚えている。その後は? 覚えていない。その前は?
■scene7 拉致

そういえば、キャバ嬢たちに見送られながら店を出る時、後藤は上田の隣に座っていたキャバ嬢を指さし、2ブロックに向かって、声を殺してこんなことをささやいていた。
「オレはいいんだけどさぁ、あんなバカなこと言ってくれちゃったらさ、コイツが、上田が怒るだろ」。
そのキャバ嬢が不用意に発言した「ピンハネ云々」のことを後藤は詰っていた。
2ブロックもチャラ男もスキンヘッドも、後藤に対して平身低頭し、上田に対しても苦虫をつぶしたような表情を浮かべて詫びを入れた。後藤に一気をさせられてフラフラしていた上田は顔の前で手を大きく振った。
逆恨み。きっとそうだ、そうに違いない。お得意さんの後藤からのクレーム。しかし、上田をないものにしてしまえば、そのクレームもなかったものになる。
「さらわれたんだ」
アイツらが眠っている自分を拉致して、この海に連れてきた。上田はそう直感した。暖かな海風を受けながら、上田はぞっとした。きっと、この海に沈められる。キャバクラのドアの前に立っていたスキンヘッドの黒服の姿が脳裏によみがえった。抵抗しても、絶対にかないっこない。上田は、はじかれるように全力で走りだした。
松林の向こうに見えた建物を目指して5分ほど走っただろうか。遠くからは低層マンションのように見えたが、どうやらオフィスビルのようだった。腕時計を見る。9時を少し回ったところ。すでに人間が活動を始めている時間。ここまで来れば大丈夫…。
正面エントランスまで来るとようやく走るのを止め、膝に手をついて、肩で息をした。崩れ落ちるようにして階段に腰掛け、したたる額の汗をTシャツの裾でぬぐった。突然、左の背後から声をかけられ、ビクッとした。
「キミが上田クン、かな?」
声の主は、レーサーパンツをはき、サイクルジャージ姿でサイクルヘルメットをかぶり、ロードバイクを引いて笑顔を浮かべていた。黒服たちの仲間ではない、と直感した。
『誰だ、コイツ?』
そう思いつつ、上田は息を切らせながら答えた。
「ハァ、ハァ…。はい、上田ですけど。ハァ、ハァ」
はい、上田ですけど、あなたは誰ですか? そう聞こうとして、息が切れて後半の言葉は呑み込むしかなかった。
「あぁ、やっぱりね。そんなにあわてて走って来なくても。ウチの会社には定時っていう概念はないから。いつ出社してきてもいいし、好きな時間に退社していいんだよ。まぁ、そこに座ってないで、中に入ろうか、上田クン」
自分と同じくらいの年齢の見えるその若い男は、IDカードのようなものをセンサーにかざして自動ドアを開き、上田をビルのなかに誘い入れながら、ヘルメットを脱いで簡単な自己紹介をした。
「ボクの名前は相座健人。誰かが『アイザだから、アイザック・ニュートンのニュートンでいいんじゃない』って言いだして。ボクもまだ入社して1週間くらいで、まだ社内には定着していないニックネームだけど、“ニュートン”って呼んでいいからね。よろしく」
そう言ってニュートンはロードバイク用のグローブをはめている右手を差し出し、上田と握手をした。
自動ドアを入ると、そこはもうオフィスフロアで、数人の人が出社していた。白を基調としたオフォスは床から天井まで全面ガラス張り。朝陽が燦燦と降り注ぎ、まぶしいくらいだった。
「おはよう」
入り口から10メートルほど離れた海をのぞむ大きな窓を背にした社員らしき男から声をかけられた。逆光で上田の位置からは男の表情は見えなかったが、ニュートンと同じようなラフな軽装だった。
「あ、おはようございます。今朝はシリコンバレーとネットMTGでしたよね」
「うん、敵はクロノスだ」
社員らしき男は数回首を左右に振りながら踵を返してオフィスの奥にある階段に向かって歩きだし、トントンと階段を昇って行った。
ニュートンはロードバイクをオフィスのなかに持ち込み、自動ドアを入ったすぐ左手の横の広めのスペースにとめた。すでに2台のロードバイクが置かれていて、サーフボードも何枚かたてかけられていた。
■scene8 TOMS
「上田クンのデスクはボクの隣で、ホラ、あそこのオリーブの鉢植えのところ。ちょっとシャワーを浴びてくるから、デスクで待っていて。それにしてもすごい汗だよね。上田くんにもシャワーを浴びてほしいところだけど、マイバスタオルがないと使っちゃいけないルールなんだ。あそこにあるウォーターサーバーは自由に使っていいからね」
ロードバイク用のグローブを脱ぎながらニュートンはそう言い残すと、オフィス内の自転車置き場とは反対の右手の廊下の向こうへにスタスタと歩いて行った。
オフィスビル、ロードバイク、シリコンバレー、サーフボード、自分のデスク、それにシャワー…。脈絡のないモノ・コトの連続で、上田はポカンとするしかなかった。
ウォーターサーバーの冷たい水をたっぷり喉に流し込んでから、ニュートンに指示されたデスクに座った。席と席の間が広々とし、決まった方向ではなく、それぞれ好き勝手な向きにデスクが配置されている。そんな様子を見ながら、上田は疑問を整理した。
「ここはどこで、なんの会社なのか。なぜ初対面なのにニュートンは自分の名前を知っているのか」―
10分ほどしてニュートンが戻ってきた。紺の半ズボンと大きな胸ポケットがついたオレンジ色のポロシャツに着替えていた。そして上田の隣に座るやいなや、説明を始めた。
「上田クンの仕事は、うちの会社がつくっている新しいタイムマネジメントツールの開発プロジェクト、“TOMS”というコード名なんだけど、そこにジョインしてもらうこと。プロジェクトチームがあるのは湘南本社オフィス、つまりここなんだ。SEベンチャーからタイムマネジメントのインフラを開発する企業への業態転換をかけたプロジェクトなので頑張って。上場も近いしね」
なめらかな、マシンガンのようなニュートンの早口が心地よく耳に響く。
「ボクが初対面の上田クンの名前と顔を知っているのは、夕べ、TOMSの新しいプロジェクトメンバーとしてキミの顔写真とプロフィールが、ボクの『AKASHI』に送られてきたから。ボクはこの会社で人事をやっていて、当面、上田クンをサポートするのがミッションのひとつってわけ。わかった?」
上田の疑問をすべて見透かしていたようにスラスラと説明するニュートン。つじつまは合っている。ただひとつ、まったく身に覚えがないことを除いては。上田はあわてて、こんな質問をした。
「なんでボクが、そのプロジェクトメンバーにくわわって、この会社で働くことになってるんですか?」
「さぁ、そこまではわからないなぁ。キミが望んでいたんじゃないの? とにかく今朝、会社の玄関にキミはいたんだから」
ニュートンは少し首を傾げながら答えた。
「いや、そういうことじゃなくて、なぜ自分はここいるんですか?」
上田は聞きたいことと回答が噛み合わないことをもどかしく感じた。だが、自分のベッドで寝て起きたら海で、どうやらこの会社で働くことになっているという、この理解不能な状況をうまく説明できる言葉がなかなか出てこない。
「まぁ、キミの実力を会社が評価しているのは間違いないので、それがTOMSのメンバーにジョインしてもらうことになった最大の理由なんじゃないかな」
ニュートンはなだめるような口調で答えた。
「あぁ、はい…」
理解できるが納得できない解説だった。でも“実力を評価した”という言葉がうれしかった。それに、「そんなの知らない」といまオフィスを飛び出すと、あのスキンヘッドの黒服が出てきそうな気もした。そこで上田は『いったん様子を見よう』と決めた。
「じゃあ、この会社のことから教えるね。まず、PCを開いて、タイムカードに打刻しようか」
PCを開いてタイムカードに打刻!? タイムカードと言えばレコーダーにカードを突っ込む古臭い装置しか知らなかった上田には意味がわからなかったが、言われるままPCを開いた。
「そのまま2秒くらいじっとして。内蔵カメラが上田クンの網膜をセンシングするから。うん、いま『読み取りました』というアナウンスがPCから流れたよね。これで打刻は終了。さぁ、仕事を始めよう」
「キミが上田クン、かな?」第2話 おわり
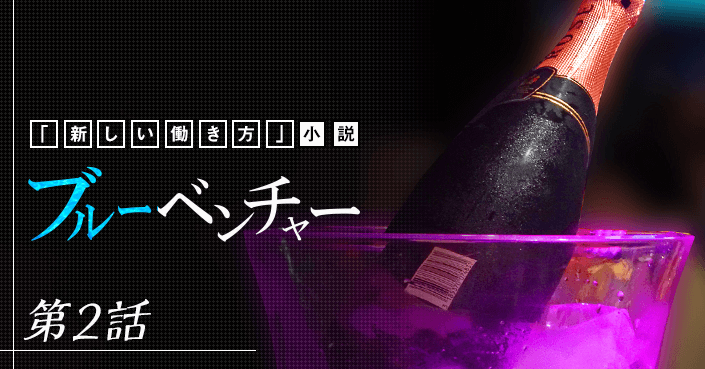
【連載小説】ブルーベンチャー |
クラウド型勤怠管理システム「AKASHI」
勤怠管理システムを導入することで、効率的かつ確実に労働時間を管理することが可能となります。ソニービズネットワークス株式会社が提供するクラウド型勤怠管理システム「AKASHI」は、36協定設定、年休管理簿や労働時間の把握など、あらゆる法改正や複雑な就業ルールに対応する機能をフレキシブルに対応します。15年以上のノウハウを活かした充実のサポート体制で導入後も安心です。
今ならAKASHIのサービスを30日間無料でお試しいただける無料トライアルを実施していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。