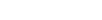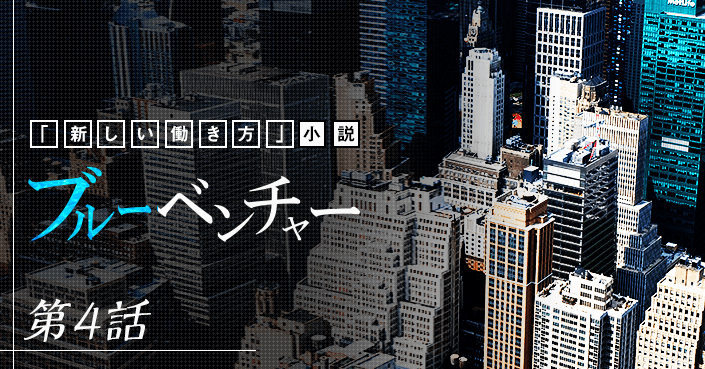
| <前回までのあらすじ>「TOMSプロジェクト」 第3話
自宅マンションで目を覚ました上田の衣服から貝殻や海の砂が出てきた。ニュートンから手ほどきされた新しいタイムマネジメントのあり方を鮮明に思い出し、上田は後藤に電話をし、後藤の仕事をすべて断りたいと申し出た。 ※この小説はフィクションであり、実在の人物・団体などとは一切関係ありません。 |
■scene12 転換
具体的には、TOMS特区においては法定労働時間ではなく、法定“休息”時間を設定することで、サービス残業などの矛盾を解消する実証実験を行うというのだ。「働く時間」を管理しようとするから、さまざまな抜け道ができる。そこを逆に「働かない時間」を管理するという発想の転換で生産性を上げようという試みだ。
「働かない時間」を管理することは、多様な働き方を後押しする、と記事は続ける。「〇時間以上は働かない」とすることで仮に働き手が足りなくなったときは、法定“休息”時間の枠に余裕のある人に勤務してもらうことで充足をはかるのだ。これにより、子育て、介護、病気などで長時間の連続勤務が困難な人たちにとっても、それぞれのライフスタイルあった短時間で断続的な働き方が可能になる、としている。
ダブルワークも後押しする。会社に勤務していても、季節変動になどよる繁閑の差で「働かない時間」の余裕が生まれた場合、他社で短時間勤務することを容易にするからだ。
企業側にも大きなメリットがある。連続勤務に拘泥している場合、拘束時間内に生じる、実質的にその人が「働いていない時間」にも給与を支払うことになり、それが生産性を下げる一因にもなっている。一方、「働かない時間」のタイムマネジメントを軸に据えて短時間の断続勤務を取り入れれば、そうした企業経営上のムダを取り除くことができる、というのだ。拘束時間イコール「働いている時間」ではなく、24時間マイナス「働いていない時間」イコール「働いている時間」という発想だ。
だが、それを可能にするには、きめ細かいタイムマネジメントが必要だという大きな問題もある。一日のなかで何度も切り替わるオンタイムとオフタイムを捕捉するためには、「出勤・退勤」の2項目しかない従来のタイムレコーダーではまったく間に合わない。アナログ方式から、項目数を無限に増やせるデジタル方式への転換が不可欠だ。
さらに、デジタルならなんでもよいというわけではない。労務管理と連動している必要があり、さまざまなデバイスで打刻できるものでなければならない。そして、それによって、さまざまな人が、さまざまな場所で、さまざまな働き方ができる。「働き方」の姿が一変するのだ。
記事には、長時間連続勤務の弊害について触れた、遠慮のないコラムもあった。従来の「働く時間」のタイムマネジメントによって、長時間労働が称賛され、長い時間働くことが“美徳”であるかのような価値観が社会に広まっていることが、さまざまな不幸をもたらし、生産性の向上を阻害しているのだと。
それがどれだけ不健全で、働く人の健康と精神をむしばみ、結果として会社の生産性を下げているのか。企業側は自社の生き残りをはかるためにも、そのことに早く気づくべきだとしている。「低収益」と「長時間労働」はセットで、どこかでこの連鎖を断ち切らない限り、企業は激しい国際競争の中で生き残れない。こうした新しい働き方は、ベンチャーが先陣を切るべきだ。コラムはそう結んでいる。
新しいタイムマネジメントがもたらす福音と、旧来の労働者管理の古い手法が招く悲劇。雑誌記事はふたつの観点から、経営者と働き手が直面している問題を分析し、大胆に未来を予測していた。
特集記事を読み終えて、上田は自身を取り巻く世界が大きく転換しようとしている、その節目に自分が立っていることを実感した。同時に、これほど大きなトピックを自分がキャッチアップできていなかったことに驚いた。仕事に疲弊し、新聞やテレビのニュースを見る時間は減っていた。それにしても、自分の情報アンテナがこれほど低かったとは。経営者として失格だな、と自分を呪った。
■scene13 違和感
記事には数多くの識者が登場していた。政府関係者、行政、大手の民間企業だけではなく、社会学者、物理学者、医師、漫画家、さらにはデザイナーやラッパーなど。時代の先端にいて影響力をもっている人たちが共鳴している「TOMSプロジェクト」には、国民運動しての大きなうねりをもっていることが感じられた。
上田は記事に登場する人物が書いた本や資料を図書室から次々と引っ張り出した。コーヒーテーブルの上に、あっという間に書物の山ができた。
ぐぅ~~っ。自分のお腹の中から間の抜けた音がした。どれくらい時間がたったのだろう。時間を忘れて夢中になって資料を読み込んでいたが、腹のムシは食事の時間がきたことを知らせてくれた。まだ読んでいない本は明日にまわすことにして、いったんどこかで食事をしよう。そう思って引っ張り出した資料を片付けていたときだった。
「初日からあんまり飛ばさないで。まだ先は長いんだから」
背後からニュートンの声がして、上田は後ろを振り返った。
「もしかしたらと気になっちゃって様子を見に来たんだ。ボクの家から会社まで、ロードバイクを飛ばせば5分くらいで来れるし」
ニュートンは言い訳するような口調で上田を気遣った。
「おもしろくて夢中になって。すっかり時間を忘れちゃった。特にこの記事の、この一節。見てくださいよ」
上田はそう言いながら、スクラップファイルにとじられていたTOMSプロジェクトの特集記事のコラムのなかのお気に入りのフレーズを探し出すため、文字を丹念に指で追った。ページの右下隅にそのフレーズを見つけ、指でおさえつけてニュートンに見せようとしたとき、上田は違和感を抱いた。
たいていの雑誌は、左ページなら左下隅に、右ページなら右下隅に、その雑誌の誌名、発刊年月日、そしてページ数が小さな文字で印刷されている。上田が気に入ったフレーズは、まさに発行年月日の真上にあった。そこには「2020年7月号」という小さな文字。いまは2015年のはずだ。ありえない発行年月日。ミスプリントなのだろうか。上田の思考が止まった。
「時を味方に、か。うん、いい言葉だね」
背後からスクラップ記事をのぞきこんでいたニュートンが、上田が指でおさえていたフレーズを読み上げた。
「2020年って、一体…」
上田はそうつぶやくと、自分の顔のほとんど真横にあったニュートンの顔を凝視した。目と目があった。先に視線を外したのはニュートンだった。
「上田クン、海まで散歩しようか」
落ち着いた声でニュートンは上田を誘った。
時刻は夜の20時を少し回ったところだった。ニュートンと外に出るため、社内を横切ると、まだ数人の人が働いていた。でも、朝に見た顔とはまったく別の人たち。何時に来て何時に帰るのかわからないけど、これがいま働いている人たちにとって、もっともパフォーマンスが上がる働き方なのだろうと上田は思った。
図書室を出た右斜め前は、ガラス張りのトレーニング室。そこでは老若男女、さまざまな年齢層の男女4~5名が、器具を使って思い思いにトレーニングをしていた。ニュートンはそのなかから顔見知りを見つけ、初老の男性に向かって会釈をした。
その男性がランニングマシーンを停止させると、カードリーダーからカードがすっと出てきた。首に巻いたタオルで汗をぬぐいながらカードを抜き出し、トレーニング室から出てきてニュートンに声をかけた。
「前に行っていた月会費制の『KINGSジム』は、行った日も行かなかった日もお金をとられていたわけでしょ。でも、ここの『AKASHIジム』は分単位の課金料金制で利用できるから、ムダがないよね。実にいいね」
そう言いながら初老の男性はシャワー室へと消えて行った。
「このジムは、本当はうちの会社の社員用なんだけど、社会実験の一貫で地域の人たちにも開放しているんだ。いまの人は社員じゃなくて、ボクが住んでるマンションの大家さん」
ニュートンが説明してくれた。
■scene14 波

オフィス奥の階段の上から、数人の若い男女が楽しそうに会話をしながら降りてきた。英語だった。
「彼らはシリコンバレーのラボから出張してきたエンジニアたち。短期の出張だから日本時間で働いてもらうんじゃなく、シリコンバレーの現地時間に合わせて働きたいって。『AKASHI』でタイムマネジメントしているから、こんな働き方も簡単なんだ」
みんながみんな、最大のパフォーマンスを発揮できるよう、自分のスタイルで働いている。その価値観は、地域社会に広がっている。時間を追いかけたり、時間に追われるのではなく、時間を味方につけて、自分らしく働き、生きている。
自動ドアを抜けて外に一歩踏み出すと、潮の香りがまじった海風がおだやかに吹いていた。
「わかったことがあるんだ。オフ、つまり働いていない時間って、怠惰に休憩する時間じゃないんだ。オンがアウトプットする時間なら、オフはインプットする時間。時にはアウトプットに専念してもいいし、インプットに集中してもいい。そのバランスをとることが重要なのであって、それが崩れるとオンもオフも辛いものになり、生産性が落ちる」
上田は並んで歩くニュートンに、熱を帯びた声で語りかけた。
「本当のタイムマネジメントっていうのは、管理して人を縛り付けるものじゃなく、逆に自分をしばっているものから解放し、人々を幸せにするためにオンとオフのバランスを調和させる、見えない分銅のようなものなんだ」
ニュートンは静かにうなずき続けた。
ふたりは砂浜に腰を下ろした。途中、自販機でニュートンが缶ビールをふたつ買い、1本を上田に投げて寄こしてくれた。砂浜に座り、プルタブを同時に開け、夜の闇の向こうで寄せては返す波の音をかなでている海を見やりながら、ゆっくりと味わうように、ビールを飲んだ。ニュートンが缶を見詰めながらつぶやいた。
「人間って、どこからきてどこに行くんだろうね」
「ボクは今日、自分のマンションの部屋で寝ていて、この海岸で目覚めた。そして、これからどこに行くのか、それはまだわかっていない」
上田がニュートンの口調を真似て言った。ニュートンは口元をほころばせながら上田を見て、砂浜であおむけになった。
「今日はきれいな星空だ。こんな日にキミと出会えてうれしかったよ」
上田も砂浜にあおむけになった。しばらくふたりは押し黙っていた。寄せては返す波の音が無言を埋めた。
「上田くんが読んでいたあの記事のなかに、ラッパーが出てきたよね。アルベルトっていう変わった名前のラッパーだったと思う」
上田の脳裏に「2020年7月号」という、ありえない発行年月日の文字がよみがえった。
「アルベルトっていうのは、アインシュタインのファーストネーム。いまのボクのニックネームは、苗字の相座からの連想で、ニュートン。アイザック・ニュートンだ。でも、ボクはニュートンが発見した万有引力という一方向の絶対的な力は、それほど好きじゃない。時間や空間は伸び縮みするっていうアインシュタインの相対性理論のような、柔軟な構造のほうが好きだ」
ビールの酔いがまわったのか、夜空一杯に光る星々の姿がボヤけてきた。上田はまどろみたくなり、目をつむった。寄せては返す波の音。時間は海の波のようなものなのかもしれない。一方向だけに進むんじゃなく、寄せては返す、柔軟な動き方をしているのかもしれない。時を味方につければ、そんな時間の波に乗ることも可能なのかもしれない。
「最初はボクも信じられなかった。ここが未来の世界なんだって。上田くんに会えてよかったよ。だから、アルベルトという風変わりなラッパーの名前は、どこかで覚えていて」
ニュートンは、会った時からよどみのない流れるような早口だった。テンポよくリズミカルに言葉がつむぎだされ、事実の説明なのに意思をもった主張のように聞こえる、独特な言葉使いだった。ニュートンはもう一度、言った。
「上田くんと会えてよかった」
ニュートンの声がフェードアウトしていく。かわりに頭のなかが波の音で満たされていく。引き波の音に吸い込まれるように、上田は眠ってしまった。そして、次に目が覚めたのは、自分のベッドの上だった。
「人間って、どこからきてどこに行くんだろうね」第4話 おわり
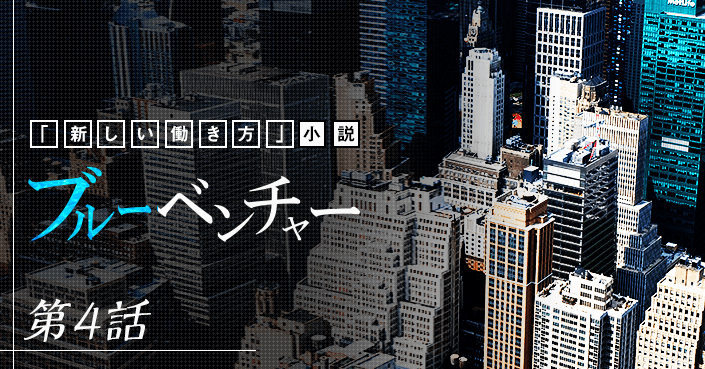
【連載小説】ブルーベンチャー |
クラウド型勤怠管理システム「AKASHI」
勤怠管理システムを導入することで、効率的かつ確実に労働時間を管理することが可能となります。ソニービズネットワークス株式会社が提供するクラウド型勤怠管理システム「AKASHI」は、36協定設定、年休管理簿や労働時間の把握など、あらゆる法改正や複雑な就業ルールに対応する機能をフレキシブルに対応します。15年以上のノウハウを活かした充実のサポート体制で導入後も安心です。
今ならAKASHIのサービスを30日間無料でお試しいただける無料トライアルを実施していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。