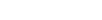ノーレーティングとは、従業員をランク付けせず、1on1などを通じて継続的に評価・フィードバックを行う制度のことを指します。リアルタイムで成長や成果を反映でき、納得感やモチベーション向上につながります。一方で管理職のマネジメント能力への依存や、管理職の負担増といった課題もあります。多くの場合、給与は上司の裁量で予算内に配分されます。今回は、ノーレーティングのメリット・デメリット、給与の決め方などについて解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>ノーレーティングとは?
従来のレーティングとは異なる新たな人事評価制度
ノーレーティングとは、人事評価制度において「レーティング(ランク付け)」を無くす取り組み、またはランクを付けない評価手法そのものを指します。否定形の印象から誤解されることもありますが、人事評価制度そのものを無くそう、という取り組みではありません。
ノーレーティングにおいては、従来のランク制度で年度単位・四半期単位といったスパンで行われていたレーティングを廃止し、代替として1カ月単位で行われる1on1面談などによって、より短いスパンでの人事評価を行います。なおその際は、次月の目標設定も同時に行われることが多いようです。
ノーレーティングが注目を集める背景
ノーレーティングという概念が注目されるようになった背景としては、主に「社会の流動化」と「人事評価制度の複雑化・陳腐化」の2点が大きいとされています。
現代社会においてはIT化やDXの進展により、受発注から製品・サービス提供に至るまであらゆるビジネスシーンのスピードが加速し、社会の流動性が高まっています。それに伴い、旧来の人事評価制度は多様な評価項目のニーズに応えるべく複雑化する一方、評価関連事務はいっそう煩雑化し、そうした激しい変化に対応しきれなくなっているという矛盾を抱えていました。
これらの課題を一挙に解決する手法として、「そもそも煩雑なレーティングをしない」ノーレーティングという考え方が注目を浴びるようになったのです。
ノーレーティングにおける給与の決め方
ノーレーティングにおいては、当然ながらランク付けによる一律の給与水準が適用できません。そのため、給与の決め方については導入企業により差異があるのが現状です。
一例として、給与の決定権が管理職にある場合、利用可能な人件費について予算担当部門から事前に共有がなされます。管理職はその後、ノーレーティングの評価結果に基づき、かつ与えられた予算の範囲で部下へ給与を配分することになります。
総じて、ノーレーティングでの給与の決め方はその評価方式と同様、流動的なものであるといえるでしょう。
ノーレーティングの4つのメリット
メリット1:目標設定や評価に納得感がある
ノーレーティングにおいては、定期的な1on1を介した密なコミュニケーションにより、目標設定の精度や、評価制度への納得感が従来型の人事評価よりも高まる効果が期待できます。そのためには、画一的な視点ではなく、従業員個人の資質・適性に応じた評価視点が重要です。
メリット2:従業員のモチベーションが上がる
給与が短いスパンでの評価に応じて流動的に上下することで、従業員はより高い評価を目指すべく、さらなるモチベーションを持って業務に携わることができる可能性があります。また、短期目標の定期的な更新がなされることで、自身が身につけるべきスキルの明確化にも役立つでしょう。
メリット3:環境の変化に対応できる
先述したように、ノーレーティングは社会の急激な変化に対応すべく取り入れられた手法でもあります。市場におけるさまざまな競争や、消費者の価値観の変化はもちろん、戦争などの社会情勢や災害といった不確定な環境下であっても、時勢に応じた適正な評価の維持が期待できるでしょう。
メリット4:多様な働き方に対応できる
レーティングが存在しないことは、雇用形態や業種の多様化にも有利に作用する可能性があります。例えば米国で一般的な「ジョブ型雇用」は、職務に必要なスキルに応じて事前に人事評価を行い、雇用中はその達成度に応じた「職務給」が支払われる雇用形態であり、ノーレーティングの仕組みと好相性といえます。
その他、正社員とその他の雇用形態の間で生じていた、評価制度の不平等や給与水準の格差といった諸問題を解決できる可能性もあるでしょう。
ノーレーティングの2つのデメリット
デメリット1:管理職の負担が大きく高いマネジメント能力を求められる
ノーレーティングにおいては、旧来の評価制度において一律の目安となっていたレーティングが存在しないことから、評価者である管理職は部下一人ひとりに対して詳細な分析・評価を下す必要があります。公平かつ適正な評価のためには、広い視野や深い業務知識のみならず、個人の行動様式や資質への注目という相反する視点も要求されるため、より高度なマネジメント能力が求められることは疑いようがないでしょう。
デメリット2:すべての組織に合うわけではなく混乱を招く恐れもある
こうした管理職の負担増に加え、業種や組織構造によってはそもそもノーレーティングの導入が向いていない、あるいは浸透に時間がかかることもネックとなりえます。1on1による定期面談は、ポイント制の評価シートなどの方式よりも時間や手間がかかる上、各人の目標設定も頻繁に変更されることになりがちです。社員が導入の必要性を感じていなかったり、導入によりかえって混乱が生じたりすると、先に挙げたようなメリットが期待しづらくなってしまうでしょう。
まとめ
ノーレーティングは、従来の人事評価制度への複雑化・煩雑化といった不満と、社会の流動化・不確定化によるスピード感向上の要請という、2つの側面に対応できる制度です。月単位など、より短期間で給与と評価が連動する仕組みでもあることから、客観性・正当性がきわめて重要となります。また、従業員個々人にフォーカスした適正な評価を実現するため、管理職にはより高度なマネジメントスキルが求められます。導入にあたっては、自社の業務分野や組織構造との相性を見極めながら、管理職に適した人材の確保が可能かという点からも、慎重に検討する必要があるでしょう。