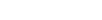クロスアポイントメント制度とは、大学や研究機関、企業など複数の組織に所属しながら活動できる制度を指します。研究者が専門性を活かして複数機関で業務を担うことで、知の循環やイノベーション創出を促進します。人件費や研究環境の最適化につながる一方、契約管理や労務の調整など留意点もあります。制度を効果的に活用するためには、関係機関の連携体制や役割分担の明確化が重要です。今回は、制度の概要や導入のメリット、注意点などについて解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>クロスアポイントメント制度とは?
研究者等が複数の組織で活動できる制度
クロスアポイントメント制度とは、研究者や技術者が単一の大学・研究機関、あるいは所属企業といった枠組みに囚われず、複数の組織と契約を結んで働いたり、研究活動に従事したりすることを可能とする制度です。
経済産業省においては、主に人材流動性の向上、若手研究者の活躍機会創出を目的として、本制度の積極的な利活用を推進しています。また、クロスアポイントメント制度の利用における基本的枠組みや、組織間で締結する協定書のひな形、留意点に関するQ&Aといった資料も同省より公開されており、導入検討の参考となるでしょう。
雇用形態としては企業間における「出向」に近く、実際に先述の資料では「在籍型出向」の一形態としても扱われています。
クロスアポイントメント制度の仕組み
クロスアポイントメント制度では、連携する組織間で協定書を作成し、それぞれの組織で従事する業務の割合(エフォート、従事比率)に応じて、各組織での業務時間・給与等を調整するのが特徴です。出向元での労働時間が0、出向先が100といった、従来の「出向」と同様のケースも想定されます。
そして、研究者は各機関と個別に労働契約を締結し、協定書の内容に応じて利用可能な研究設備・人材といったリソースを用い、時には知的財産に関する情報共有も行いつつ研究に従事することとなります。
また、給与面については従来の「出向」とは異なり、協定書によって規定されるほか、連携の成果や貢献度に応じてインセンティブを上乗せすることが推奨されています。このようなインセンティブを含めた給与、および各種社会保険料の支払い主体については、複数組織が按分で支払うことも可能ではありますが、収受手続きに支障が生じないよう、単一の組織が全額を負担することが多いようです。
兼業・副業や共同研究との違い
クロスアポイントメントと同様に、複数の企業が関係する業務のあり方として、兼業・副業や共同研究が挙げられます。それぞれとの相違点は以下の通りです。
- 兼業・副業
兼業・副業は、複数企業で同時に業務に従事、または個人事業を営み、複数の収入源を得る労働形態です。兼業・副業を行う個人は、それぞれの企業と独自に雇用契約(または請負契約など)を締結するため、クロスアポイントメントのようにエフォートに応じた業務配分や、給与・インセンティブの調整は行われません。
また、副業には「本業に対して、片手間で行う業務」といったニュアンスがありますが、クロスアポイントメントにおいては、どちらが本業・副業であるかといった概念は特段重視されません。 - 共同研究
共同研究は、複数の組織を跨いで研究成果(および知財や設備)の共有を行う際、その方法や範囲等についてあらかじめ取り決めをしておく連携方式です。多くの場合、クロスアポイントメントにおける協定書と類似した「共同研究契約」を組織間で締結します。しかし、研究者はあくまでも単一の組織に所属した状態で研究を進めるため、業務時間に関する取り決めは基本的に盛り込まれません。したがって、給与については所属する組織からのみ支払われるという相違点があります。
クロスアポイントメント制度を導入するメリット
研究者のメリット1:柔軟な研究活動を実現できる
クロスアポイントメントで締結される協定書では、基本的に労働条件やリソース、知財の共有について主眼が置かれています。研究分野や範囲については、利益相反とならないよう組織に資する必要こそありますが、研究者自身が比較的自由に活動内容を設定することが可能です。そのため、研究の指針が定められていることの多い共同研究と比べ、柔軟な研究活動が実現しやすいといえます。
研究者のメリット2:組織のリソースを有効活用できる
クロスアポイントメントでは、複数の組織が保有する物的・人的リソースに加えて、予算の利用といった点も協定に盛り込まれます。これにより、単一の研究者だけでは実現不可能だった規模の研究や、高度な実験環境の活用が可能となることで、より社会的意義・付加価値の高い成果を挙げやすくなる可能性があるでしょう。
組織のメリット1:大学の研究活動が活発になる
大学と企業等の間でクロスアポイントメントを実施する場合、大学側は前述のように、企業が保有する資産の一部を利用できる可能性があります。連携する企業の設備投資や、協定書で定める範囲にも左右されますが、大学のみで研究開発を行うよりも周辺環境が充実している場合、より活発な研究活動が期待できるでしょう。
組織のメリット2:企業の技術開発が促進される
企業相互でのクロスアポイントメントにおいては、秘密保持のためにこれまで公開されてこなかった技術・ノウハウについても、一定の共有が期待できます。企業の垣根を超えた技術開発・革新が成功すれば、よりいっそう競合との競争力向上が見込まれるでしょう。また大学や研究機関で培われた、これまで市場で注目されてこなかった専門知識の吸収においても、同様のことがいえます。
クロスアポイントメント制度の注意点
注意点1:労働契約
クロスアポイントメント協定書において給与を定める際には、出向元と出向先の給与水準差に応じて高い方を適用するほか、インセンティブを付与することが推奨されています。また、出向者が契約社員等の「有期雇用労働者」や、パートタイマー等の「短期雇用労働者」に該当する場合、同一労働同一賃金原則の適用対象となる点にも注意が必要です。
さらに、労働条件が出向先の退職金支給要件に該当する場合、原則として契約終了時点で出向先からの支払い義務が発生します。トラブルを避けるため、あらかじめ協定書に対象外とする旨を盛り込んでおくなどの対策が求められるでしょう。
注意点2:社会保険
企業が負担する社会保険料のうち、医療保険・年金に関しては、給与の支払い主体となる企業がその額に応じて保険料を支払う形となります。雇用保険についても同様ですが、被保険者は「主たる賃金を受ける一つの雇用関係についてのみ、その被保険者資格が認められる」点に注意が必要です。協定にあたっては、たとえ給与の支払い元が分かれていたとしても、複数組織を跨いだ加入ができない点に留意しましょう。
まとめ
クロスアポイントメント制度は、導入により大学・企業といった組織の枠を超えた、研究者の自由な研究活動を促進する効果が期待できます。ただし導入に際しては、本制度を推進する経済産業省の資料等を参考に、給与体系・社会保険の負担といった実務面の理解を深めることが前提となるでしょう。
また連携する組織の担当者だけでなく、研究者個人も協議に参加し、業務に応じた納得できるインセンティブを設けることで、研究開発を促進できる可能性が高まります。企業間だけでなく産学連携も視野に入れた、幅広い利活用が期待できる制度といえるでしょう。