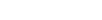内部監査とは、組織内の業務やプロセスが適切かつ効率的に行われているかを評価・検証する活動を指します。法令遵守や内部統制の強化、業務改善の推進などが目的とされています。一般的な流れとして、監査計画の策定、監査対象の選定、資料収集・分析、監査結果の報告、改善提案の実施が含まれます。適切な内部監査を通じて、組織の健全な運営と持続的な成長が促進されます。今回は、内部監査を実施する目的や流れなどについて解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>内部監査とは?
内部統制を確認し不正やミスを防ぐ手段
内部監査は、企業が顧客・株主・取引先といった各ステークホルダーからの信頼を損なわないよう、独立した内部監査部門を設けて企業自らチェックや評価を実施する活動です。法令違反の原因となる意図的な不正や、意図しない誤謬(ミス)の発生を未然に防ぐため、各部門のチェック機能となる「内部統制」が適切に機能しているかどうかを、全従業員を対象として確認します。内部監査の結果は経営者へ報告され、業務効率化や改善に役立てられます。
外部監査や監査役監査との違い
同様のチェック機能には、内部監査以外にも「外部監査」「監査役監査」が存在します。これらは監査を実行する主体と、監査の及ぶ範囲が異なり、それぞれが独立しつつも補完的な関係にあります。
「外部監査」の場合、監査の範囲は内部監査と同様ですが、監査を担当するのは監査法人所属の公認会計士をはじめとした有資格の第三者であり、一定の客観性が確保されていることが特徴です。
一方で「監査役監査」は、株主総会で選任された監査役が「取締役の職務執行が適正かどうか」についての監査を行い、株主へ報告するものです。こちらは取締役の職権を主眼に置いた監査であり、従業員を対象とする内部監査・外部監査とは主となる目的が異なります。
主体と範囲こそ異なりますが、いずれの監査についても「当該企業の業務が円滑に、職権の乱用や違法行為なく行われているか」をチェックする機能という点は共通していると言えるでしょう。
内部監査を実施する目的
法令遵守や内部統制の強化
内部監査では、社内での業務プロセスや別会社との取引の中で、法令違反が行われていないかを徹底的に調査します。こうした法令違反行為を予防するため、社内ルールや管理態勢を整備することを「内部統制」と呼びますが、内部監査はその綻びを発見するための重要な手段です。会社法で「大会社」と定義される規模の大きな企業や、会計参与を設置せず取締役会のみが設置されている企業については、同法によって内部監査が義務付けられています。
業務改善の推進
内部監査がもたらす内部統制の強化にあたっては、業務効率、企業内外へ行う報告の信頼性、資産の保全といった業務改善も目的として含まれています。内部監査の義務がない中小企業の場合でも、こうした経営の健全性を保つだけでなく、上場審査の際に内部統制の体制が整備されている必要があるため、早い段階から内部監査を実施する企業が少なくありません。
内部監査の流れ
監査計画の策定
はじめに監査人の選定と、内部監査全体の工程を決める監査計画を策定します。監査の公平性・客観性を保つため、監査人には基本的に監査対象の部署とは関連のない人物を選ぶのが適切です。内部監査を初めて実施する企業の場合は、監査の進め方に関するマニュアルもこの時点で作成しましょう。
監査対象の選定
監査対象の部署を決め、必要に応じて予備調査を行います。スムーズな監査を実施するためには事前に資料や証憑の提出を求める必要がありますが、法令違反の調査を主目的とする場合は、証拠の隠ぺい等を防ぐために監査当日まで対象部署に通知しないケースもみられます。
資料収集・分析
収集した資料や証憑・帳票類を基に、場合によっては責任者や現場の担当者といった従業員へのヒアリングも交えつつ、業務プロセスの妥当性や違反の有無についてサンプルを抽出して分析します。主要な確認事項については、監査計画の時点でチェックリストを作成しておくとよいでしょう。
監査結果の報告
監査結果を内部報告書にまとめ、経営者へ報告します。法令違反のみならず、社内規程や事業所単位での業務マニュアル、コンプライアンスといった細分化した観点からも、抜けがないかチェックしましょう。
改善提案の実施
報告結果を鑑みて、改善案を具体的に提示することも内部監査の主な役割です。内部監査のフィードバックが対象部署の効率改善に寄与し、ひいては企業全体の利益となるという意識が浸透すれば、改善意識の向上だけでなく、次回の監査時の協力も得られやすくなると考えられます。また必要に応じて、改善状況を確認するフォローアップ監査を実施したり、監査のマニュアル自体も部署ごとに最適化したりするなど、内部監査そのものをより効率化していくことも検討しましょう。
まとめ
内部監査は、内部統制が適切に行き届いているかを経営者が確認する機会であるとともに、普段は目の届かない各支店・部署へ問題点を指摘し、改善策を提案するひとつの手段でもあります。未上場の中小企業にとっては実施の義務こそありませんが、業務効率の向上とリスク管理は事業の規模を問わず、あらゆる業態において重要です。ステークホルダーから企業への信頼性をより盤石にし、持続的な成長へ寄与する効果もあるため、実施を検討しておくのもよいでしょう。