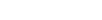カッツモデルとは、組織内の役職に応じて必要とされるスキルを3つに分類した理論です。現場では技術的な「テクニカルスキル」、中間管理職では対人関係力である「ヒューマンスキル」、経営層では全体把握や戦略立案に必要な「コンセプチュアルスキル」が重視されます。職位に応じたスキル育成や人材配置に活用でき、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。今回は、カッツモデルの構成や実践的な活用法を紹介します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>カッツモデルを構成する階層
トップマネジメント
カッツモデルにおいて職位・役職を分類する3階層のうち、最上段にあたるのがトップマネジメントです。CEOなどの経営者をはじめとした、組織の意思決定に関わる幹部・役員クラスが該当します。トップマネジメントは主に後述するコンセプチュアルスキルを活かし、経営戦略やビジョンを明確にし、それに向けて組織全体のマネジメントを行う立場です。そのため、現場の一般社員ほど実務的なスキルや、業務についての詳細な知識は求められない傾向にあります。
ミドルマネジメント
2段目のミドルマネジメントには、部長・課長・係長・プロジェクトマネージャーといったいわゆる「中間管理職」クラスが該当します。トップマネジメントが策定した方針・戦略に基づいて、ロワーマネジメントを筆頭とした部下を統率する立場となるこの階層は、組織全体のパフォーマンスを決定づける重要な役割を担っています。組織全体をある程度俯瞰・理解した上で部下に浸透させる能力と、部下の実務に対する管理能力の両方が必要とされ、後述する3つのスキルのバランスが重要です。
ロワーマネジメント
3階層の最下段にあたる管理職がロワーマネジメントです。ミドルマネジメントの下でプレイヤーを束ね、より実務的な指揮を執る立場にある、係長・主任・チーフ・プロジェクトリーダーといった職位が該当します。この階層ではいわゆる「業務遂行能力」と呼ばれるような、より詳細な実務の知識・スキル・経験等が求められ、翻ってトップマネジメントやミドルマネジメントほどは、組織全体を見渡す視点は求められません。
カッツモデルにおけるスキルの分類
ヒューマンスキル
ヒューマンスキルは、上記3分類のどの階層においても一定水準以上が求められるスキルです。主にコミュニケーション能力・問題解決力・共感力・プレゼンテーション能力など「人間関係を円滑にする」「意思疎通を適切に行う」ためのスキルがこれにあたります。組織が一枚岩となって目標に向けて行動するために、各マネジメント階層が必ず身につけていなくてはならない基礎的なスキルといえるでしょう。
テクニカルスキル
テクニカルスキルは、上記3分類の中では「ロワーマネジメント」における重要度が最も高く、どちらかといえば実践的といえるスキルです。テクニカルスキルの内容は業種・職種によって異なり、商品知識・説明力・事務処理能力や、PCスキル・プログラミング能力といったものまで多岐にわたります。
またミドルマネジメントにおいては、求められるスキルの性質がプレゼンテーション能力・リサーチ力・分析力といった、よりマクロで俯瞰的なものに変化していく傾向にあるようです。テクニカルスキルの求められる比重は、トップマネジメントに近づくほど低下するとされています。
コンセプチュアルスキル
コンセプチュアルスキルとは「conceptual(概念的な)」の名が示すように、テクニカルスキルとは逆に「トップマネジメント」における重要度が高く、より現場に近い下層へ移行するごとに占める比重が下がるスキルです。このスキルが指す能力は抽象的な要素を多分に含みますが、あえてまとめるなら「複雑な事象の集合体を概念として捉えたうえで、本質を理解する力」と言い換えることができます。
組織が直面している課題を具体化し、対応方針を策定するために有効な論理的思考力・水平思考・クリティカルシンキングといった思考法に加え、洞察力や未来予測力といった外部要因に対する「先見の明」も必要とされる高度なスキルです。
カッツモデルの活用方法例
評価項目の設定・分析
人事評価においては、カッツモデルの3階層とそれに合わせた想定スキルを評価項目に取り入れることで、評価制度をより精緻化するとともに、組織の人材全体のマネジメント能力底上げを見込める可能性があります。従来の評価項目をヒューマンスキル・テクニカルスキル・コンセプチュアルスキルの3分類に細分化し、各マネジメント階層で求められるスキルレベルや比重に応じた評価基準を設定することで、個々人の達成度やキャリアアップへの適性を分析しやすくなるでしょう。
階層別のスキルマネジメント
個々人のスキルの習熟度を可視化できれば、当人がキャリアアップに足りないスキルを認識しやすくなり、特定のスキルに的を絞ったセルフエデュケーションの意欲を向上させられる可能性があります。また、組織側から講演への参加や研修といった教育の機会を提供可能な場合は、そこへ積極的に参加してもらうといった効果も見込めます。
研修内容のカスタマイズ化
対象者の現在のマネジメント階層に応じて、提供するスキルの内容を適宜カスタマイズすることによる、人材マネジメントの効率向上も期待できる効果のひとつといえます。組織における限られたリソースを適切に配分するためには、個々の研修や教材が可能な限り高い効果を挙げることが必要です。例えば広範な分野を詰め込むのではなく、ターゲットとする人材や扱うテーマを絞り込んで短期集中とすることで、時間的・金銭的コストを抑えつつ人材育成に貢献できる可能性があります。
まとめ
カッツモデルで分類される3つのスキルは、3階層それぞれで求められる比重が異なり、それらを意識した人事評価・人材育成施策を行うことで、人材ごとに適切なキャリアプランを歩むことができる組織づくりへの活用が見込めます。組織力の総合的な底上げにもつながる可能性があるため、汎用的な人事評価の適用に課題を感じている組織であれば、取り入れてみるのも一考でしょう。