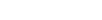寛大化傾向とは、人事評価において評価者が本来の基準より甘く点数をつけてしまう傾向を指します。寛大化傾向によって、評価の信頼性が損なわれ、適切な人材育成や配置が困難になります。原因としては評価者の遠慮や関係性への配慮が挙げられ、対策としては評価者研修や評価基準の明確化が有効です。今回は、寛大化傾向の概要と発生原因、企業が取るべき対策について解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>寛大化傾向とは?
実際より高く評価してしまう心理的バイアスの一種
いささか古い情報ではありますが、1990年に日本経営工学会誌に掲載された論文「人事考課における寛大化傾向・中央化傾向・厳格化傾向の定量的分析」では、寛大化傾向を「評定者が被評定者を実際にあるより も高い方向に評定してしまう傾向」と定義しています。具体的には、人事評価において、評価者が本来の基準より甘く点数をつけてしまう傾向が「寛大化傾向」です。人事評価における偏向には優れた特徴が他の評価にも影響を及ぼす「ハロー効果」や、本来の基準より厳しく点数をつけてしまう「厳格化傾向」などがあり、寛大化傾向もそういった心理的バイアスの一種といわれています。
寛大化傾向の発生原因
寛大化傾向は評価者が被評価者と距離が近すぎるがゆえに起きやすい評価エラーでもあり、具体的には「部下によく思われたい」「部下に嫌われたくない」「低い評価をつけることに負い目を感じる」といった心理状態が影響しているといわれています。とりわけ低評価に対する負い目はある種の甘さに直結し、人事評価においてもっとも重要な「公平性・公正性」を損なう大きな要因の一つです。一方、評価者自身が低評価の責任を取りたくないがために、中庸な評価に終始してしまうケースも散見されます。曖昧な評価基準や評価スキルの不足もまた、寛大化傾向を助長する原因です。
寛大化傾向の具体例
寛大化傾向は具体的に、以下のようなケースが考えられます。
- 能力や業績が伴わない部下を実際より高く評価してしまう
- コミュニケーションや関係性を重視するあまり客観的に評価できない
- 低評価を下した責任を取りたくないがために中庸な評価に終始してしまう
これらのケースを見て分かるとおり、寛大化傾向にとらわれると客観性や公平性・公正性を著しく欠いてしまいます。特に、昇進や昇格といった人事的な処遇を人事評価と紐付けている場合は、従業員の能力を正しく評価し、序列化しなければなりません。寛大化傾向は人事評価制度を揺るがす恐れもあり、そのような傾向が見られた場合はいち早く改善のアクションを取る必要があります。
寛大化傾向が企業にもたらす問題
評価の甘さと基準の不統一を引き起こす
組織内に寛大化傾向が蔓延すると、評価の甘さや評価基準の不統一を引き起こす恐れがあります。評価者によって評価基準にばらつきが生じ、人事評価にもっとも重要な公平性や公正性を著しく欠く結果にもなりかねません。また、寛大化傾向によって甘い評価が常態化すると評価基準が形骸化し、人事評価制度への信頼感を損なう恐れもあります。従業員の正しい序列化ができなくなった結果、人事評価制度の破綻を招く可能性もあり、寛大化傾向は決して放置できない深刻な問題です。
低パフォーマーを見落としてしまう
本来の基準より甘く点数をつけてしまう寛大化傾向は、低パフォーマーを見落としてしまう原因にもなります。低パフォーマーとは、仕事に対するパフォーマンスが低く、組織が求める成果を十分にあげられない従業員です。低パフォーマーはチームのモチベーション低下、組織全体の生産性低下、優秀な人材の流出につながる由々しき存在と考えられています。寛大化傾向による甘い評価によって、問題の発見と対策が遅れた結果、フィードバックと教育の貴重な機会を逸する原因にもなりかねません。組織の生産性を損ない、ひいては企業価値をも低下させかねない深刻な問題でもあります。
組織の生産性と業績へ悪影響を及ぼす
寛大化傾向によって評価基準が曖昧になると、人事評価制度に対する信頼感が低下し、従業員のエンゲージメントやモチベーションを損なう恐れがあります。企業に対する愛着を意味するエンゲージメントが損なわれると、仕事に対するモチベーションも低下するのが一般的です。モチベーションが低い状況は仕事に対する意欲も低いため、最高のパフォーマンスを期待することはできません。適切な評価や改善が行われない状況では組織力が低下し、組織の生産性と業績へ悪影響を及ぼす可能性があります。
寛大化傾向を防ぐために企業が取るべき対策
評価基準を明確化して統一する
心理的バイアスである寛大化評価を防ぐためには、評価基準を明確化して統一することがなにより重要です。特に、曖昧な評価項目は寛大化傾向を引き起こす原因だといわれています。評価項目を細分化して具体的に定義し、評価者の主観が極力入り込まない評価基準を設けることが大切です。客観的な評価基準を明文化して評価者全体で共有することで、一貫性があり公平公正な評価を実現できます。ただし、定量評価のみに偏るのも危険です。業務への意欲や熱意など定性的な側面も汲み取れるような評価基準の構築も欠かせません。
評価者に対するトレーニングを実施する
寛大化評価を始めとした評価エラーを防ぐには、評価者に対しトレーニングや研修を実施するのも重要です。元来、バイアスに左右されず客観的な視点で他者を評価するのは簡単なことではありません。公平公正で一貫性のある評価を実現するには、評価者自身のトレーニングもとても大切です。評価者が人事評価の目的を理解し、評価基準について理解を深めて初めて、客観的で一貫性のある評価を実現できます。また、評価にはバイアスが入り込みやすいことを理解し、評価者自身の傾向や偏向を自覚することも大切です。
複数の評価者を活用して評価の客観性を確保する
寛大化評価を防ぐ上では、複数の評価者を活用して評価の客観性を確保することも重要です。いくら専門のトレーニングを受けていたとしても、1人の評価者がバイアスに左右されず客観的な評価を下すことは簡単なことではありません。評価にはバイアスが入り込むものと認識し、複数の評価者が多角的に評価することで、より客観性の高い評価を下すことが可能です。客観的で多面的な評価は納得を得やすいため、従業員の満足度を高める効果もあります。
まとめ
今回は寛大化評価について解説しました。寛大化評価とは、本来の基準より甘く点数をつけてしまう心理的バイアスの一つです。寛大化評価が蔓延すると評価基準が曖昧になり、従業員のモチベーションが低下した結果、組織の生産性や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。評価基準の明確化、評価者トレーニング、複数評価者の活用などを組み合わせ、従業員の納得が得られる評価制度を構築しましょう。