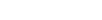セカンドハラスメントとは、被害を訴えた従業員が、周囲からの無理解や偏見、対応の不備によって二次的な被害を受けることを指します。原因としては、知識不足や組織風土の未整備などが挙げられます。対策には、相談体制の強化や対応マニュアルの整備、教育研修の実施が有効です。被害者が安心して声を上げられる環境づくりが重要です。今回は、セカンドハラスメントの原因や企業がとるべき対策などについて解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>セカンドハラスメントとは
二次被害として発生するハラスメント
セカンドハラスメントは、ハラスメントの被害を受けたことを周囲に相談したことで、二次的に発生したハラスメントのことを指します。ハラスメントの相談内容を周囲に広められてしまったり、その影響からバッシングを受けたりするケースがあり、これを「二次被害のハラスメント」としてセカンドハラスメントと呼ばれています。勇気を出してハラスメントの被害を受けたことを告白しても、相談窓口が機能していなかったり、上司をはじめ周囲の理解を得られなかったりする場合は、二次的なハラスメントとして被害者はさらに精神的苦痛を背負ってしまうことになります。
セカンドハラスメントの具体的な事例
セカンドハラスメントに該当する行為として、ハラスメントの内容を相談したところ、まともに話を聞いてもらえなかったり、被害者を反対に責めたりする、もしくはハラスメントの内容を周囲に広めてしまう、というケースなどが考えられます。被害の内容によっては、企業体制そのものに問題がある可能性があることから、相談を受けた側は組織のイメージが悪化することを懸念して、被害者側に対して追及やバッシングをしてしまったり、そもそも被害の内容をハラスメントと受け入れてもらえなかったりする場合があります。結果として、本来被害を受けている側にもかかわらず、組織の中に居づらくなってしまうほか、最悪の場合は退職せざるを得ないケースに陥る場合もあります。このようなセカンドハラスメントの行為によって、被害者はさらに精神的苦痛を強いられるようになってしまいます。
セカンドハラスメントが発生する原因
ハラスメント被害者に対する理解不足
まず始めに、ハラスメントを訴えた被害者に対する理解や、実態調査の不足が挙げられます。「気にしすぎだよ」などと軽くあしらわれてしまう、もしくは反対に叱責されるという場合、被害者やハラスメントが発生しているという現状解明が行われないため、周囲への理解が進まない可能性が高くなります。ハラスメントという行為自体を軽視していたり、企業イメージを守ることを優先したりしている環境の場合、このように被害者への理解が進まない要因となってしまいます。
「セカンドハラスメント」そのものへの理解不足
そもそも、「セカンドハラスメント」という概念や理解が進んでいない可能性も考えられます。被害者をないがしろにしたり糾弾したりする態度を上司や周囲がとってしまうのも、そもそもそれらの行為がハラスメントにあたると理解していないことから起こる現象とも言えるでしょう。このようなケースでは、無意識のうちにハラスメントの加害者になってしまう可能性があるのです。
企業内のハラスメント対策の不足
近年、パワハラやセクハラなどによる企業の不祥事が明るみに出ることもあり、ハラスメントやコンプライアンスに対する研修を行う企業も少なくないでしょう。研修を実施することはもちろん有効な対策ではあるのですが、「ただ実施して終わり」になってしまっていると、当事者意識が薄くなる受講者が増えてしまい、前述のように無意識のうちにセカンドハラスメントに発展してしまう事例が発生する可能性があります。ハラスメント対策の研修を実施する場合は、具体的な事例などを盛り込み、場合によっては誰もがハラスメントの当事者になる可能性があることを意識づけることが重要です。
セカンドハラスメントを回避するための対策
プライバシーに配慮する
ハラスメントの相談をもし受けた場合、被害者の情報を必要以上に広めないようにプライバシーに配慮した対応が求められます。もし、相談された人が自身の裁量で対処できる問題ではないと感じたら、それをなかったことにするのではなく、被害者のプライバシーを考慮したうえで上層部に対応を仰ぎましょう。実態調査や弁護士など外部に協力を依頼する場合も、不特定多数に知られないように進めていくことも、セカンドハラスメントを回避するために重要なプロセスと言えるでしょう。
ハラスメントを相談できる窓口を設置
ハラスメント被害を受けた場合、そもそも誰に相談すればいいのかわからない、というケースも考えられます。安心して被害の申告ができるように、ハラスメントの相談を受け付けている窓口を社内に設置できると、もしハラスメント被害が発生した場合の相談先としてわかりやすく提示できるため安心です。窓口から弁護士などに相談できるルートを構築しておくと、不特定多数の周囲に情報が漏れる心配も軽減でき、被害者が安心して相談できるようなプラットフォームになり得るでしょう。また、窓口が相談先として機能するためには、窓口担当者に対するハラスメント教育も入念に行うことが重要です。
社内エンゲージメントの構築
そもそも、何か困ったことや相談したいことがあったときに、周囲や上司に頼れない環境は、組織としてコミュニケーションや企業としての信頼感が不足している環境である可能性があります。安心して働ける環境を構築し、ハラスメントが発生しにくい社内環境に整え、「心理的安全性」の高い環境を構築することを目標としましょう。
まとめ
セカンドハラスメントが発生する難しさとして、自身が無意識にハラスメント行為をしている可能性があるという点が考えられます。ハラスメント被害者の対応によってセカンドハラスメントに発展する可能性があることを考慮し、企業はセカンドハラスメントの理解を深めるとともに、ハラスメント自体を発生させない環境構築を進めることが重要です。