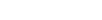スパン・オブ・コントロールとは、1人の管理者が効果的に指導・監督できる部下の人数の上限を指します。適正数は業務内容や部下の熟練度によって異なり、超過するとマネジメントが行き届かず、意思疎通や部下の育成に支障が出ます。適正化のためには業務分担の見直しやミドルマネジメントの育成が必要です。今回は、スパン・オブ・コントロールの考え方と、組織運営への影響や調整のポイントについて解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>スパン・オブ・コントロールの定義
マネジメント人数の最適化
スパン・オブ・コントロールとは、日本語に訳すと「管理限界」と呼ばれる考え方で、1人の上司が適切に部下を管理およびコントロールできる人数のことを指します。もともとはビジネスの概念ではなく、軍隊の指揮についてコントロールできる人数のことを指していたようですが、近年ビジネスシーンにおいても使われ始めている用語です。スパン・オブ・コントロールの人数を超えてしまった場合、上司は適切に部下をマネジメントできなくなり、企業全体の生産性や効率性が低下すると言われています。
適性人数は5~8人程度
スパン・オブ・コントロールの限界となる人数は、チームやプロジェクトの特徴や上司のマネジメント力、チームを構成する部下のスキルやパフォーマンス力などにより左右されるものの、一般的には5〜8人程度が限界の人数と言われています。大手小売業者であるAmazon.com の創始者であるジェフ・ベック氏は、「2枚のピザ理論」を提唱しており、これは2枚のピザを食べきれる人数、つまり10人程度を最大とすることが望ましいと説き、実際に社内でも実践しているのだそうです。
スパン・オブ・コントロールを超えた運営上の影響
意思決定の品質低下
重要な意思決定のタイミングが遅くなったり、意思決定にかかわる要素を深く吟味できなくなったりすることで、適切な意思決定が難しくなるケースもあります。意思決定を行うには部下の業務状況やヒアリングを行うことも重要ですが1人ずつ時間を割くことが難しくなるため、最適ではない意思決定の内容を上司が下してしまう可能性が高まります。
部下との連携不足
部下を受け持つ数が多くなると、その人数だけマネジメントのプロセスが発生します。すると、研修やフィードバック面接など上司と部下が直接関与し成長するタイミングが失われることになるため、部下の成長を阻害してしまう可能性があります。それだけではなく、連携や情報共有がうまく進まないことにより、業務の生産性や効率性が低下することが考えられます。
上司の業務量が増大
多くの部下を抱えると、それだけマネジメント量も増え、それぞれの質も低下してしまいます。それだけではなく、上司自身の業務も平行してこなさなければいけないことになるため、必然的に上司の負担が大きくなることが考えられます。自身の業務を優先させなければならない場合、部下との連携やマネジメントは阻害され、さらにチーム内での効率性や生産性も低下し、悪循環に陥る可能性もあります。
スパン・オブ・コントロールを調整するポイント
部下のマネジメント方法の見直し
たとえ部下の人数が多かったとしても、部下本人がやるべき仕事をこなし、生産性と効率性を高められるのであれば、おのずと上司が介入しなければならないシーンは減少します。そのため、部下に介入しなければならない時間が多いケースでは、マネジメントの方法やプロセスを見直したり改善したりすることが求められるでしょう。
これに加え、上司側が持つ意思決定権を、部下に「権限委譲」する方法もあります。もちろん、誰に委譲するのかは慎重に決定しなければいけません。しかし、部下に重要な業務プロセスを任せることで上司の負担が軽減されるだけでなく、部下自身の成長にもつながり、上司の介入がなくとも業務を効率的にこなせるようになります。
マネジメント管理のツールを導入
マネジメント管理を工夫しようと思っても、人の力だけでは限界を感じることもあるかもしれません。そのような場合は、マネジメント管理のツールの導入をおすすめします。もちろん導入の際とツールを使用するためのランニングコストはかかるデメリットはありますが、管理自動化や一つのプラットフォームで部下のステータスや業務状況をわかりやすく可視化できるのは、非常にメリットが大きいといえます。
業務プロセスや情報共有の効率化
ツール導入の話にもつながりますが、マネジメントの範囲だけでなく、普段の業務プロセスや部下と上司、チーム内、もしくは部署外や外部とのプロジェクトなど、幅広い範囲で情報共有が必要になる場合はより効率的なコミュニケーションがとれるように調整を行いましょう。情報共有や報連相の仕組みをしっかりとルール化する、業務内容をマニュアルとしてまとめ自己解決ができるように促す、などの方法を導入してみましょう。また、会議や報告などの双方向間の情報共有やコミュニケーションにデジタルツールを組み込むと、場所にとらわれることなくリアルタイムで効率的に情報周知が図られ、スムーズな業務進行につなげられます。
まとめ
1人の上司が受け持つ部下の数が多すぎると、「管理限界」を引き起こしさまざまな悪影響を及ぼします。部下のスキルやパフォーマンス力、上司のマネジメント力などによって限界を引き起こす人数は異なりますが、適切な人数があることを把握しておくと、社内全体の生産力や効率性の向上につなげることができるでしょう。