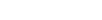ワークモチベーションとは、従業員が仕事に取り組む際の意欲や動機のことを指します。目的意識の共有や評価制度の明確化、感謝や承認の文化づくりが向上の鍵となります。モチベーションが高まることで生産性やエンゲージメントが向上し、離職防止にもつながります。今回は、ワークモチベーションの構成要素や、組織としてどのように高めていくべきかについて解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>ワークモチベーションとは?
仕事に対する意欲や動機を包括した心の動き
ワークモチベーションとは、「仕事」を意味する「ワーク(work)」に「意欲」を意味する「モチベーション(motivation)」を組み合わせたビジネス用語で、仕事に対する意欲や動機を包括した心の動きを意味します。日本語でもよく「モチベーションが低い」や「モチベーションが高い」などといいますが、意欲や動機を内包した「心の動き」全般がモチベーションです。とりわけワークモチベーションは仕事に対する意欲を意味し、企業に対する愛着を意味するワークエンゲージメントと並んで重要な要素といわれています。
モチベーションの2つの分類
日本でも「モチベーション」という言葉を耳にする機会は多いかもしれませんが、実はモチベーションは2つに分類することが可能です。モチベーションの定義には諸説あり、組織心理学で著名なヴィクトリア大学のピンダー教授は「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」の2つに分類しました。内発的動機づけは内なる要因で生まれる欲求で、例えば仕事に対する意欲はこちらに分類されます。一方、外発的動機づけは外部の要因で生まれる欲求で、評価や報酬は代表的な外発的動機づけです。個人の内部で発生する内発的動機づけはモチベーションを維持しやすいのに対し、外部からもたらされる外発的動機づけは一度満たされると満足してしまい、中長期で見るとモチベーションを維持しにくいという特徴があります。
ワークモチベーションが注目される背景
ワークモチベーションが注目を集める背景には、少子高齢化による深刻な人材不足と働き方の多様化があります。売り手市場の近年は特に人材が不足しており、採用競争の激化も深刻です。あらゆる産業が人材不足に苦しむなか、限られた人員が最大限のパフォーマンスを発揮することが求められています。従業員一人ひとりが持てる能力を最大限発揮するには、ワークモチベーションを高めることがなにより重要です。また、働き方が多様化する昨今は転職も当たり前ですが、優秀な人材を確保し続けるためにもワークモチベーションを高める取り組みが欠かせません。環境を整え仕事にやりがいを感じてもらうことで、優秀な人材の流出を防げるからです。
ワークモチベーションの構成要素
ワークモチベーションには、以下の3つの構成要素があります。
- 方向性
- 強度
- 持続性
方向性は、組織の目的を明確化し、その目的を達成するための目標や手法に関する理解を指します。強度は、組織の目的に対し、どのくらい熱意や意欲を持って取り組んでいるかの指標です。持続性は、組織の目的を達成するため、どのくらいの時間や労力を継続的に費やしたのかを示します。組織の目的を実現するには、従業員一人ひとりの意欲が欠かせません。従業員は立場やポジションが異なっても、意欲を高め合って一つひとつ目標を達成していく必要があります。そのためには、マネジメント層が従業員のワークモチベーションをコントロールすることが重要です。
ワークモチベーションの測定方法
心理尺度を用いたアンケート調査
ワークモチベーションの測定方法には2つの手法があり、1つ目は心理尺度を用いたアンケート調査です。心理尺度とは、人間の感情や行動の傾向など心理現象を数値化するために用いられる測定ツールを指します。心理尺度は主観的な心理現象を数値化し、分析しやすいのがメリットです。ワークモチベーションの測定では自己決定理論に基づく尺度が用いられます。心理尺度を用いたアンケート調査によって従業員の内発的動機づけが明らかになり、プロセス段階で動機づけを特定することが可能です。
パフォーマンス評価
ワークモチベーションの測定方法の2つ目は、パフォーマンス評価です。パフォーマンス評価とは、従業員が実際に知識や技術を使いこなす能力があるかどうかを測る評価方法を指します。単に知識や技術を身に付けているだけでなく、課題の解決や創造的な活動にそれらを活かすことができるかどうかを測定する、実践的な評価方法です。ルーブリックと呼ばれる評価基準を作成して評価するのが一般的で、実践的な能力を測定するのが目的でもあります。業務に対する積極性や組織に対する貢献度を測る方法でもあり、従業員としての成長機会や組織としての目的達成に役立つ方法です。
ワークモチベーションを高める方法
評価制度を明確化し目的を共有する
ワークモチベーションを高めるには、まずは評価制度を明確化し、組織としての目的を従業員に共有することが重要です。公平公正で納得感のある評価制度を実現できれば、それが動機づけとなり従業員のワークモチベーションは向上します。また、組織の目的を全社で共有することで、組織と従業員・従業員と従業員が互いに意識を高め合い、ワークモチベーションの向上が期待できる点も見逃せません。具体的な取り組みとして、より具体的で達成できそうな短期目標と、一見達成が難しそうな長期目標を立てて、共有することが効果的です。目標達成に向けた取り組みを評価しフィードバックを実施することで、ワークモチベーションを高められます。
感謝や承認の企業文化を醸成する
社内表彰制度やインセンティブを導入し、感謝や承認の企業文化を醸成することも重要です。具体的には、組織が従業員を・従業員が従業員を表彰することで、チームのメンバーを認め合い感謝の気持ちを伝えられます。インセンティブは目標を達成した際に支給される報奨金や奨励金を指し、目標達成に向けた大きな動機づけとなるでしょう。社内表彰制度やインセンティブによって目に見える形で感謝の気持ちを伝えることで、従業員のワークモチベーションを高めることが可能です。また、組織や仲間から認められる経験を通し、愛社精神を意味するワークエンゲージメントの向上も期待できます。
キャリアサポートを実施する
ワークモチベーションを高める3つ目の方法は、キャリアサポートを実施することです。キャリアサポートとは、従業員のキャリア形成を支援するあらゆる取り組みを指します。キャリアサポートを通して従業員が自身のキャリアパスを理解することで、仕事に対する向き合い方をあらためて認識することが可能です。キャリア形成をサポートし成長の機会を提供できれば、従業員のワークモチベーションは自然と向上します。キャリアサポートを実施するには、ヒアリングを通して従業員のニーズを把握することが重要です。ニーズに合ったキャリアサポートを提供することで、従業員はより充実したキャリアを歩むことができます。
まとめ
今回はワークモチベーションについて解説しました。ワークモチベーションとは、仕事に対する意欲や動機を内包した心の動きです。人材不足が深刻な昨今、従業員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮することが求められています。評価制度の明確化やキャリアサポートを実施することでワークモチベーションを高め、最大限のパフォーマンスを引き出しましょう。