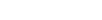サマータイムとは、日照時間を有効活用するために時計の針を1時間進める制度を指します。企業にとっては、従業員の通勤混雑緩和や業務効率の向上が期待されます。一方で、体内リズムの乱れや業務時間の調整が難しいといったデメリットも存在します。制度導入には、業種や働き方に応じた慎重な検討が求められます。今回は、サマータイムの概要と企業におけるメリット・デメリットなどを解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>サマータイムとは?
日照時間を有効活用するため時計を1時間早める制度
日本ではあまり馴染みのない制度ですが、欧米などで1日の日照時間が多くなる春から秋にかけて、時刻を1時間進めて日中の活動時間を伸ばす制度のことを「サマータイム」もしくは「夏時間制度」と呼びます。季節によって変化する日照時間の差は緯度によって異なりますが、日本の場合はもっとも日照時間の長くなる「夏至」と、反対にもっとも短くなる「冬至」の季節とでは、数時間もの差があると言われています。特に、緯度が高いため日照時間の差が大きい北欧やアメリカ、カナダなどの北米・ヨーロッパ諸国を中心として積極的に導入されている制度です。
サマータイムが求められる理由
起床や就寝時間、就労時間が同じでありながら、日中に活動できる時間が増えることがサマータイムの一番の導入理由と言えます。日本においても冬場は午後5時ごろから日が暮れ始めますが、暑い時期は午後6時以降になっても外は明るいままであることが多いでしょう。このように、明るい時間が長いことを活用し、日照時間内において効率的に行動できるようにするために、サマータイムを導入する国が多いと言われています。
日本におけるサマータイム導入の現状
日本をはじめ、アジア圏の国では、サマータイムを導入している国はほとんどありません。もともと欧米圏がこの制度の発祥ということもありますが、特に東南アジアなどの緯度の低い国においては、季節ごとの日照時間に大きな差がなく、サマータイムを導入する意味がないというのも理由の一つでしょう。
日本においては、実は戦後まもなく、1948年から1951年において試験的にサマータイムを実施していました。当時は戦争からの復興のさなかで電力不足だったこともあり、日中に活動することが非常に有意義だったことからこの制度を導入していましたが、1952年以降は廃止されています。また、自治体によってはそれ以降も試験的に導入されることがありましたが、現在まで国単位での正式な導入には至っていません。
サマータイムのメリット・デメリット
メリット1:エネルギーを節約できる
明るい日中の時間帯に活動する人や企業が増えることで、照明・冷暖房などのエネルギー消費の節約になる点です。もともとサマータイムの導入が初めて行われたイギリスやドイツなどの欧州諸国も、戦時下においてエネルギー消費を抑えるために実施されたことが始まりと言われています。現代社会においても、エネルギーの高騰や地球温暖化などの対策として、エネルギーの節約が期待できるのは大きなメリットと言えるでしょう。
メリット2:経済効果が期待できる
次に、日中の時間帯に活動する人が増えることで、レストランやカフェの利用、物品の購入、観光などの余暇といった行動パターンが増加し、経済効果が期待できる点が挙げられます。退勤時間が早まり、余暇時間が日朝時間の間に含まれる時間が長くなることで、消費者の出費が増加する効果が期待できるとされています。
デメリット1:残業時間が増える可能性がある
一方で、消費者側が経済活動を活性化させることで、小売業やサービス業などの従事者にとって、残業時間が増える可能性があることは否定できません。この場合、経済効果というメリットは最大限生かせない可能性があるため、雇用者は必要以上に残業時間を増やさないように働き方やプロセスの見直し、職場環境を整えるなどの調整を実施する必要があるでしょう。
デメリット2:システムの変更に手間やコストがかかる
標準時間からサマータイム、もしくはサマータイムから標準時間に切り替える際には、システム的な問題や作業の増加などによる手間・コストがデメリットとなることがあります。特に時間が重要な役割を果たす交通機関や企業の勤労管理などは、システムの調整や改修が必要不可欠となり、もし不具合が出てしまった場合は大きな存在が生じる可能性があります。また、サマータイムを初めて導入する場合、時間変更のためのシステムを新たに整備しなければならない点も考慮すべき点でしょう。
サマータイム導入時のポイント
過重労働にならないよう気をつける
デメリットの点でも触れたように、日中の活動が活性化することにより、一定の業種における労働者が大きな負担を強いられることがないように注意しなければいけません。特に日本は、厚生労働省のデータによると欧州諸国などと比較した場合、長時間労働者が多い傾向にあると言われています。サマータイムの導入により、これまで以上に長時間労働や時間外労働を助長させる働き方を雇用者がさせないように留意しなければ、メリットとなる経済効果を最大限に生かすことはできないでしょう。
すべての労働者に適用しようとしない
パートタイムなどの短時間労働者は、限られた時間でしか働けないという人もいます。一時間時間を早めることで、本来の労働時間とずれてしまい、その時間には出社できないケースもあるかもしれません。このような場合は、サマータイムに合わせた労働時間を強要するのではなく、各従業員の働き方に合わせてサマータイムを導入してもよい従業員、導入しないほうがよい従業員と切り分けて雇用契約を結びましょう。
労働者の健康に十分配慮する
サマータイムの導入を見送った要因の一つとして、労働者の健康に悪影響があったという声もあります。時間を早めたことで生活リズムが乱れてしまい、疲労感や生活習慣病へのリスクが高まるといった意見もありました。たった一時間だけと思うかもしれませんが、起床時間や就寝時間など、生活リズムが一時間早まるだけでも体にとっては慣れるまでは大きな負担がかかる人も少なくないでしょう。
まとめ
日照時間のうち、人間としての活動時間を最大限生かすためにサマータイムを導入している国もありますが、日本をはじめアジアの国々では現在導入率は高くありません。その裏には、システム変更の手間や残業時間の増加といったデメリットが隠されていることにありました。もしもサマータイムが導入される場合は、すべての労働者に適用しようとせず、各従業員の働き方に合わせて柔軟に対応するのがよいでしょう。